| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和23年5月1日(1948年。 三島由紀夫(23歳)が『罪びと』という、単行本の一段組で12頁ほどの短編小説を脱稿しています。
『罪びと』は次のように書き出されます。
雪のあとのまばゆい晴天へ大まかにさし出された寺院の
と、最初の1文からこの密度です。雪に清められた
2文目で、彼の屈辱が、「ここにゐる人すべての目が彼を不幸な人間として眺めてゐる」ことからくるものであることが明らかとなり、3文目で、その理由も分かります。戦後、彼が戦場から戻るとその直後に
4文目、5文目、6文目は、その新たな謎への応えです。護が出征するとき(「死んでこい」と強いられたとき)、人々は同情しなかった(同情するのを遠慮した)。その同じ彼らが、「同じ一つの死」に対してなのに、異なる反応をしていることへの反感。周りの空気で拵えられている人々の脆弱な感情の場に、死の当事者としていなくてはならないのが、護には「屈辱」以外の何者でもなかった──。
ここまででようやく一段落。半頁ほどの分量(全体が12頁なので、そのおよそ24分の1)なのに、すでに読者を沈思に誘う内容があります。一文一文に、鮮烈な映像的イメージがあったり、それに呼応した鋭い心理描写があったりで、それぞれで一句がひねれそうな密度です。
『罪びと』を脱稿した昭和23年5月1日(三島23歳)のちょうど22年後の昭和45年5月1日、三島(45歳)は、彼の小説で一番の長編となり、また、遺作ともなる『
書き出しは、
沖の
と短い文を重ねています。なんとその後、4頁にもわたって海と空が描出され、「話者」(小説の中で語っている人。著者とは区別される)は、その海と空の状態・変化に「意味」があると感じており、それにぼんやりと見入っているのでした。
『罪びと』の場合は、廂からたえまなく落ちる滴を見ている護を見ているのは、もちろん護なのではなく、護の外側の、特に誰とは特定されない人であり(「中立の視点」)、護がそのとき突然感じた「屈辱」も見透かしている「神の視点」(全てが分かっている立場)です。「神の視点」で描くと、スパッ、スパッと鮮明なイメージを切り取って、物語をぐいぐい先に推し進めることができるかもしれません。かたや「天人五衰」では、「沖の霞が遠い船の姿を幽玄に見せる」と感じているのが誰なのか、つまり話者が誰なのか明かされないまま、延々と海と空が描出され、4頁目の最後でようやく、
──安永透は倍率三十倍の望遠鏡から目を離した。
と、空と海を眺め思いに沈んでいるのが、駿河湾を臨む通信所で船舶の出入りを監視している、
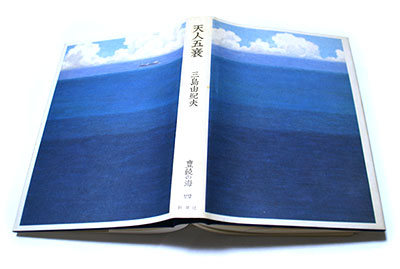 |
| 「天人五衰」のカバーを描いたのは杉山
|
「小説の形」(テキスト量の寡多)は、視点提示のタイミングだけでなく、文体や全体の構成(プロット)にも当然影響するでしょう。芥川龍之介の死から2ヶ月もたたない時期に、芥川を偲んで書かれた「
川端康成には『雪国』といったそこそこの長編小説がありますが、実はこれは、複数の雑誌(7誌)に12年間にもわたって発表された中短編小説の集合体で、それぞれを単独作品として読むこともできます。鎌倉を舞台にした『千羽鶴』『山の音』、無敗の名人・本因坊秀哉の引退碁について書かれた『名人』も、同様の方法で発表されました。
星 新一に代表される「ショート・ショート」という、短編小説よりもっと短く、数ページで完結する小説があります。「ショート・ショート」の先駆とされる城 昌幸の作品集『怪奇製造人』には30篇も収録されていますが、その中でも一番短い「古い長持」(3ページ)という小説を読んでみました。
・・・桐の葉が、軒に音をたてて散るのを聞いていた、お婆さんが、突然こんなことを
「あの、中二階の奥にござンしたね、古い長持が」
夕刊を眼鏡越しに読んでいたお爺さんは、ちょっと顔を上げただけだった。
「ここへお嫁にきた晩、あなたは、こわい顔なすって、あの長持は決して開けてはいけないとおっしゃいましたね。・・・・(城 昌幸「古い長持」の冒頭)
「ショート・ショート」に限って言えば、「釣られて」「背負投げを食らわされる」のも悪くないかな?
 |
 |
| 松本和也『テクスト分析入門 〜小説を分析的に読むための実践〜』(ひつじ書房) | 菅原克也『小説のしくみ 〜近代文学の「語り」と物語分析〜』(東京大学出版会) |
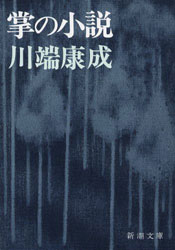 |
 |
| 川端康成『掌の小説 (新潮文庫) 』。2〜10頁ほどの短編を122編収録。清水 宏監督の映画「有りがたうさん」の原作「有難う」もその一篇 | プルースト『失われた時を求めて〈1〉 (光文社古典新訳文庫)』。「20世紀最高の文学」にして最長の小説。冒険的読書となるだろうか? |
■ 馬込文学マラソン:
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
・ 志賀直哉の『暗夜行路』を読む→
・ 川端康成の『雪国』を読む→
・ 城 昌幸の『怪奇製造人』を読む→
■ 参考文献:
●『三島由紀夫研究年表』(安藤 武 西田書店 昭和63年発行)P.63-67、P.308 ●『決定版 三島由紀夫全集17』(新潮社 平成14年発行)P.775-779 ※解題 ●「「神の視点」という小説の表現法」(本条克明)(文章は時空を超えて→) ●「清水港と三島由紀夫『天人五衰』(豊饒の海・第四巻)」(なべさん)(なべろぐ→) ●「沓掛にて」(志賀直哉 昭和2年発表(志賀44歳))※『志賀直哉全集 第六巻』(岩波書店 平成11年発行)に収録 ●『雪国(川端康成全集 第五巻)』(新潮社 昭和44年発行)P.388
※当ページの最終修正年月日
2023.5.2