| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和5年1月1日(1930年。 牧野信一(33歳)の短編小説『ラガド大学参観記』(青空文庫→)が「文藝春秋」に発表されました。
スウィフト(1667-1745)の小説『ガリヴァー旅行記』(Amazon→)に出てくる科学都市・ラガドには飛行機のようなものや、人造人間や、バーチャルリアリティのようなものも存在します。『ラガド大学参観記』はそのラガド(過去の創作物)の「現在」を描いた小説です。
この頃の牧野には実験的な小説をたくさんあり、『ラガド大学参観記』が収録されている作品集『西部劇通信』(牧野が当地(東京都大田区)にいた頃出版された)には、他にも面白いものが並んでいます。
『西部劇通信』の最初を飾る「川を遡りて」(青空文庫→)は、仲間と原始生活を始めるけれども、食料に事欠き、“武装”し“略奪”の旅に出るというものです。「今」を書いているのに、実際の今とは相当ずれています。
2作目の「パンアテナイア祭の夢」(青空文庫→)にも、いつもの朝方の物語に、若者がいつも朝方走らせる馬車の中で読んでいる過去の物語(ギリシャの物語)が入り交じってきます。
3作目の「
 |
時間の表現の基本は、「朝起きて、顔を洗って・・・」といった感じに過去の一点から現在に向けて順に語られるパターン。現在に近い状況(「謎」)を冒頭にポンと持ってきて、「実は、・・・」と順に語られるパターンも、推理小説などによくありますね。
高村 薫の『レディ・ジョーカー』(Amazon→)(当地(東京都大田区)が主要な舞台となる)では、最初、昭和22年に書かれた議事録と長い手紙が提示されますが、その後、時間がジャンプして43年後の平成2年に。冒頭の文書がなぜ提示されたのかさえ分かりませんが、その後、企業、警察、検察、新聞社のシビアーな現場が分刻みで緊密に描かれ、その理由が徐々に解けてきます。
・・・合田は午後九時四十五分に団地へ引き返し、洗濯機を回した。次にテレビをつけ・・・(中略)・・・辞書に手を伸ばしたところで、電話が鳴った。受話器を取り上げるとき、習慣で時刻を確かめた。午後十時五十五分だった。・・・(中略)・・・付近は静かで、住人の気配はなかった。合田はその前で自転車を止め、まず時刻をたしかめた。午後十一時七分。 ・・・(中略)・・・報告を聞く間に、腕時計の長針はまた一目盛り進んだ。十一時十分。車が着いたという十時五分から、経過すること六十五分、と合田は頭に刻んだ。・・・(中略)・・・時刻は午後十一時二十一分。事件が発生したと思われる時刻から、七十六分が経過、もう緊急配備は無理だった。 ・・・(高村 薫『レディ・ジョーカー』より)
ドストエフスキー(日本の小説家に一番影響を与えている小説家かも)の『罪と罰』(Amazon→)。では、緻密な心理描写が続くので長い時間が経過しているものと思いきや、ラスコーリニコフが金貸しの老婆を殺してから自首するまではわずか12日間ほどなのですね。「忠臣蔵」で有名な浅野内匠頭の江戸城・松の廊下での刃傷と彼の切腹、イエスの最後の晩餐と彼の処刑も1日のうちの出来事です(ユダヤ教では夕方から夕方までが1日)。
苦痛や屈辱が連続すると、心理的な時間が長く長く感じられることは、誰しも大なり小なり体験するところと思います。ナチスの強制収容所に送られた精神科医のヴィクトル・フランクルは著書『夜と霧』(Amazon→)で、収容所では1日が途方もなく長く感じられ、1日が1週間より長く感じられるという「逆説的」な時間体験を告白しています。
20世紀を代表する小説の1つ、プルーストの『失われた時を求めて』(Amazon→)は、日本語訳で原稿用紙1万枚にもおよぶ大作ですが、「マドレーヌの一きれをやわらかく溶かしておいた紅茶」を口にもっていった“瞬間”に甦って来た「失われた時」を書いたものなのだとか。
一生涯の物語を辿りながらも、実はご飯が炊き上がるまでの束の間に見た夢だったと分かる「
映画「猿の惑星」(昭和43年公開)(Amazon→)は、人工冬眠装置で生きながらえながら長い長い時間を飛行し続けた宇宙飛行士を乗せる宇宙船がとある惑星に不時着します。その惑星では、猿が支配者。人間は下等動物として、現在、人間が他の動物にしているのと同じように檻に閉じ込められています。物語は進み、最後の方で、じつはその惑星が地球であることが明らかになります。
未来といえば、三島由紀夫の遺作「天人五衰」(Amazon→)(『豊饒の海』第4巻)は、三島が自死する昭和45年から5年後の昭和50年までの時代設定になっているとのこと。近未来を書いたのですね。
「東京新聞」の夕刊に連載された
映画だと、映画の中で流れる時間と、映画の上演時間とのかね合いをどうするかといった問題も出てきます。フレッド・ジンネマン監督の「真昼の決闘」では、悪漢4人が町に戻ってくるまでの約1時間30分が、上演時間の約1時間30分とほぼ一致するように作られています。刻々と迫り来る正午(真昼)を観客も追体験できる仕掛け。西部劇転換期(無敵のヒーローが活躍する活劇中心でない西部劇が撮られた始める)の傑作です。
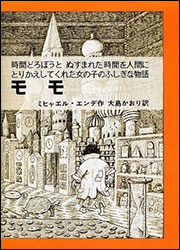 |
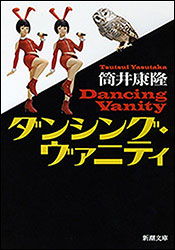 |
| ミヒャエル・エンデ『モモ(岩波少年文庫)』。盗まれた時間を取り戻そうとする、粗末な身なりの少女・モモ | 筒井康隆『ダンシング・ヴァニティ(新潮文庫)』。執拗なまでに繰り返される時間と微妙なズレ |
 |
 |
| 『〈現在〉という謎 〜時間の空間化批判〜』(勁草書房)。編著:森田邦久。物理学者の考える「時間」と、哲学者の考える「時間」 | 高水裕一『時間は逆戻りするのか 〜宇宙から量子まで、可能性のすべて〜 (ブルーバックス)』(講談社) |
■ 馬込文学マラソン:
・ 牧野信一の『西部劇通信』を読む→
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『牧野信一全集<第六巻>』(筑摩書房 平成15年発行)P.615、P.648-P.650 ●『牧野信一と小田原』(金子昌夫 夢工房 平成14年発行)P.4-18、P.34-86 ●「読書ガイド」(亀山郁夫)※『罪と罰(3)(光文社古典新訳文庫)』(ドストエフスキー 平成21年初版発行 同年発行2刷)に収録。P.468 ●『夜と霧』(ヴィクトル・フランクル みすず書房 昭和36年発行)P.174-175
※当ページの最終修正年月日
2025.1.1