| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
第1回「
 |
昭和4年9月6日(1929年。
、「東京府美術館」(現「東京都美術館」(東京都台東区上野公園8-36 Map→)で、第1回「
龍子は最初、挿絵や洋画を描いていましたが、大正3年(29歳)頃日本画に転身。大正6年(32歳)、日本画最大の“権威”「日本美術院」(「日本美術院」が主催する展覧会が「院展」)の同人に推挙されます。「日本美術院」の中でも当初から特異な存在として注目されていましたが、昭和3年(43歳)そこを辞し、翌昭和4年6月(44歳)青龍社の設立を発表、その3ヶ月後に第1回「青龍展」を開催しました。「30にして立って、40にして迷わず」の言葉が頭にあったかもしれません。
明治31年に設立された「日本美術院」も、最初は、日本美術学校(現・東京芸術大学)から排斥された岡倉天心を中心に結成された反主流の団体でしたが、岡倉と一緒に同校を辞した橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草らに加え、小林古径、奥村
挿絵画家だった龍子は、国民新聞社や実業之日本社といった新聞社や出版社とつながりがあり、マスコミの役割や有用性を理解していたのです。「日本美術院」のお歴々がマスコミの悪口を言っているのとは逆に、龍子はそれを積極的に利用しようとしました。時代の要請や関心に即して描くといった龍子の傾向(後に戦争画も多数描く)は、青龍社設立と同時に加速しました。
さらには、「会場芸術」を推進させようとしました。明治以後、美術の発表の場が美術館や画廊となって「会場芸術」の時代に入りましたが、会場の大きさと解放性が生かされていないと龍子は不満でした。「日本美術院」は同人が多数いたでしょうから、展示する作品の大きさに制限があったことでしょう。 龍子は「青龍展」で、 会場の広さを生かし切って迫力のある作品を発表して鑑賞者のど肝を抜きたいと考えたようです。第1回「青龍展」で龍子が発表した「鳴門」(上図参照)は、幅8mを越し、群青の絵の具だけでも3.6kg使ったそうです。この1作で、青龍社は存在を大いにアピールしたことでしょう。
龍子の心境は以下のようでした。
・・・私にはどうも回避とか
・・・繊細巧緻なる現下一般的の作風に対しての健剛なる芸術に向っての進軍である。・・・(「青龍社第1回展覧会出品目録」より)
・・・
 |
 |
| 青龍社の面々。龍子は垂れ幕の左下あたりにいる。第1回「青龍展」の会場入口にて ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『川端龍子(現代日本の美術13)』(集英社) | こちらも第1回「青龍展」時のもの。「東京府美術館」の入口に立つ龍子 ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『画人生涯筆一管』(川端龍子) |
力道山も大相撲で結果を出していましたが、出身が朝鮮半島ということで周囲から差別・蔑視され、絶えかねずに大相撲という“権威”を飛び出しました。それだけの才覚と勇気があったのはもちろんのこと。才覚は十分でなくても、勇気があり、それに才覚が付いてきた面もあることでしょう。
小島政二郎が心の支えにした一冊、ロマン・ローランの『ジャン・クリストフ』の主人公・ジャン・クリストフ(ベートーヴェンとトルストイとミケランジェロとミレーが合体したような人物!)は、既存の“権威”をものともしない音楽家ワーグナーの革新性に惹かれ、「ワーグナー協会」なるものに所属します。ところが、その協会のメンバーたちは、ワーグナーを“権威”として崇めており、あまりにワーグナー的(非権威主義的)でないのでした。「権威」自体は素晴らしいはずなのに、当人や周囲が「権威主義」に陥るともうダメですね。
“権威”やその周縁には、おそらく序列があって、席の順番があり、写真が飾られたり飾られなかったり、先生と呼ばれたり呼ばれなかったりで、そこに身を置けば、知らず知らずそういった仕組に取り込まれていくことでしょう。自分でやりたいことがある人には耐え難いことです。
長渕作品の頂点「Captain of the Ship」。いろいろあっても、「明日、船を出して」「お前が舵を取れ」と。
 |
 |
| なだ いなだ『権威と権力 〜いうことをきかせる原理・きく原理〜 (岩波新書)』 |
 |
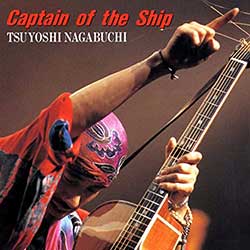 |
| エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』(東京創元社)。訳:日高六郎。自由に伴う孤独や責任から逃れ、権威や権力に寄って、加害者になっていないか? | 長渕 剛「Captain of the Ship」。いろいろあっても、明日、船を出して、お前が舵を取れ、と。守・破・離 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 『北園克衛詩集』を読む→
・ 村松友視の『力道山がいた』を読む→
・ 小島政二郎の『眼中の人』を読む→
■ 参考文献:
●「公益財団法人 日本美術院/沿革 概要/年譜」(site→) ●『川端龍子(現代日本の美術13)』(集英社 昭和51年発行)P.84-86、P.135-136(※年譜(編:土屋悦郎))●「日本美術院」(佐伯英里子)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に掲載(コトバンク→) ●『画人生涯筆一管』(川端龍子 東出版 昭和47年発行)P.132-135、P.153-173、P.382-P.385 ●『力道山がいた(朝日文庫)』(村松友視 平成14年発行)P.334-335
※当ページの最終修正年月日
2024.9.6