| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和14年4月7日(1939年。
、片山広子(61歳)が、
・・・御あいさつもいたさず中途で失礼いたしましたのは何といふわがままな物のわからぬ人間と恐縮いたしております。自分のみぐるしいかたちを一度の写真にものこしたくないと思ひましたのはもうずつとむかしの事で今更のとしになつてまでにげかくれいたしませんでもよろしいのでございますが、どうした事かやつぱり長いとしつきのくせが出まして失礼いたしました・・・
何かの会合があってその記念の集合写真の段になって挨拶もしないでその場を去った非礼を詫びています。
片山の写真嫌いは徹底しており、家族の写真はたくさんあるのに、片山はほとんど写っていません。
片山はなぜそんなに写真を嫌ったのでしょう。上の手紙には「自分のみぐるしいかたちを一度の写真にものこしたくない」とありますが、片山の評伝を書いた
 |
若い頃の片山の写真。片山の夫の妹の子孫が保管していた。お見合い写真だろうか ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『片山廣子 〜孤高の歌人〜』(短歌新聞社) |
「写真」という言葉は、紀元400年代から中国の文献に見られ、写実的な肖像画を指しました。日本にも伝わって、1300年ほども経過した1700年代半ば(江戸時代中期)になってようやく肖像画に限らずリアルな絵画全般を指すようになるようです。
司馬江漢はオランダから伝来した「写真鏡」(「カメラ・オブスキュラ」Photo→)という写生補助装置を自作し、リアルな絵を描きました。「カメラ・オブスキュラ」は、密閉された内部が真っ暗な箱の一点に穴を開け(または一箇所にレンズを取り付け。ピンホールカメラや一眼レフカメラと同じ原理)、外部の様子の天地左右逆の像を箱内に投影させるもので、さらに鏡に写して反転像を元に戻し、その像をなぞればリアルな形を得ることができました。フェルメールも使用したとの説があります。この原理で得た像を感光性のある板や紙に定着させたものがいわゆる「写真」です。
 |
1827年(1826年とも)、フランス人ニエプスが撮影した「ル・グラの窓からの眺め」。現存する最古のカメラ写真とされる ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:ハリー・ランソム・ ヒューマニティーズ・リサーチ・センター所蔵作品 |
日本人で最初に写真に撮られたのは、嘉永3年(1850年)に遠州灘で遭難した播磨の樽廻船「栄力丸」の乗組員たちです。2ヶ月間ほど漂流したあと、日本領の東端・南鳥島付近で、米国の商船に救助され、翌年(1851年)にサンフランシスコの写真館で撮影されました。最初の写真からまだ四半世紀ほどですが、クオリティが驚くほど向上しています(参考サイト:CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ)/永力丸乗組員5人の写真→)。
その9年後(1860年)、勝 海舟らと咸臨丸で渡米した福沢諭吉(25歳)が、15歳くらいの米国の娘と2人で撮られた写真(Photo→)も有名です(写真館にたまたまいた娘に「一緒に写真を写ろう」と福沢が声を掛けた)。福沢は花柳界で遊ぶことを潔しとしなかったので、仲間から硬いやつ、妙な奴と思われていたようですが、この写真を帰路のハワイを出たあたりで仲間に見せ、「こんなことはお前たちにはできまい」と彼らの鼻を明かしたようです。
 |
上野彦馬 |
その6年後の安政4年(1857年)、薩摩藩の蘭学者が撮影した島津
 |
カメラが急速に普及するのはライカなど小型で高性能のカメラが作られてからでしょうが(ライカの市販1号機は大正14年(1925年)販売)、萩原朔太郎は、それよりも20年以上も前の明治35年(1902年。朔太郎15歳)にフランス製の「ステレオカメラ」(双眼鏡のようにレンズが2つあり、双方から同時に撮影して立体感を出す)を入手し盛んに撮影しています。当地(東京都大田区)を撮ったものもあります(作品1(「品鶴線」(東京都品川と神奈川県鶴見を結んだ鉄道。現在はJR横須賀線が走る)の線路を歩く子ら。うち一人は娘の萩原葉子)→ 作品2(東京都大田区馬込あたり)→)。
・・・記録写真のメモリィを作る
当地には、片山広子という大の写真嫌いの文学者と、萩原朔太郎という大の写真好きの文学者いたのですね。
 |
ドビュッシーの紹介者として知られる大田黒元雄と写真との関わりも深いです。大正10年には福原信三(後の資生堂社長)らと写真芸術社を設立し、同人誌「写真芸術」を発行しました。朔太郎が写真で詩情(郷愁)を表そうとしましたが、大田黒は写真に音楽の形式を応用しようしています。1枚の写真を主題として、その変奏(バリエーション)としてのショットを重ねました(作品1→ 作品2→)。
・・・平凡のうちに非凡を発見する事、
写真が世界を変えることもあります。ベトナム戦争の最中、沢田教一が現地で撮った写真(「泥まみれの死」「敵を連れて」「安全への避難」など)は、世界的に広く紹介され、世界的な反戦運動の契機になりました。
 |
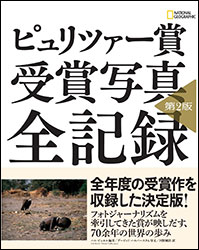 |
| 鳥原 学『日本写真史(上) (中公新書)』 | ハル・ビュエル『ピュリツァー賞 受賞写真 全記録』(日経ナショナルジオグラフィック社) |
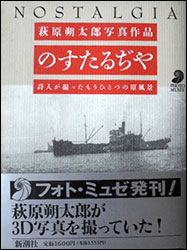 |
 |
| 『のすたるぢや 〜詩人が撮ったもうひとつの原風景〜(萩原朔太郎写真作品)』(新潮社) | 新藤健一『写真のワナ〜新・写真の読み方〜』(情報センター出版局) |
■ 馬込文学マラソン:
・ 片山広子の『翡翠』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
■ 参考文献:
●『片山廣子 ~孤高の歌人~』(清部千鶴子 短歌新聞社 平成9年初版発行 平成12年発行3刷)P.66、P.81-84 ●『日本写真史(上)(中公新書)』(鳥原 学 平成25年発行)はじめに、P.4-8 ●『福翁自伝』(福沢諭吉 時事新報社 明治32年発行)P.196-198 ●「馬込文士村 面影めぐり」(「タウンボイス(大田・品川区版 No.24)」(朝日新聞社 平成18年3月5日)) ●『大田黒元雄の足跡 ~西洋音楽への水先案内人~』(東京都杉並区立郷土博物館 平成21年発行)P.15-26 ●「萩原朔太郎 ステレオカメラ、詩人の切りとる大正・昭和の風景写真」(逸話のうつわ→)
※当ページの最終修正年月日
2025.4.7