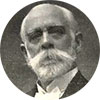| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
 |
ハリス |
黒船来航(1853年)から7年、この頃から明治になるまでに、日本にはどのような外国人がいて、どのような活動をしていたのでしょう。
幕末までの日本の鎖国体制は以下のようでした。
江戸初期はキリスト教は禁じても、海外との貿易は盛んでした。それが、
長崎に来航したのはオランダ船と中国船のみ。しかも、取引額は厳しく制限されました。
朝鮮とは、対馬藩主の宗氏を通して交流。慶長12年(1607年)から文化8年(1811年)までの間に12回「通信使」(3回までは「回答兼刷還使」)という使節を江戸に迎えています。440名を超えるほどの行列をなしましたが、オランダに対してとは違い、費用は沿道の大名や地域の人々の国役負担とされ、賓客として丁重に迎えられました。日本が西洋の知識と技術を先んじて取り入れて天狗になって、朝鮮を軽視・蔑視するようになるのは明治になってからです。
琉球王国(現在の沖縄)に対しては、日本(薩摩藩)は、慶長14年(1609年)頃から侵略的・侮蔑的な外交を展開してきました。現在に連なる沖縄問題は、江戸の初期からの歴史を踏まえる必要があります。
以上のように江戸時代は、長崎、対馬、薩摩、松前の4つの窓口に限定して、外国人(琉球人やアイヌを含む)と接してきました。
シーボルト |
シーボルト (アレクサンダー) |
オランダ船がもたらすヨーロッパ情報は幕府にとって貴重で、オランダ商館の100〜150人を定期的に江戸に招き交流しました。莫大なその費用をオランダが自弁したのは、独占的な貿易に旨味があったからと推測されています。オランダ人の江戸参府は幕末の嘉永3年(1850年。黒船来航の3年前)まで167回行われました。オランダ人がもたらす西洋の学問・技術を「蘭学」といい、青木
シーボルトは「シーボルト事件」(日本地図を国外に持ち出そうとして処罰された)により国外追放処分となりますが、その追放令が解除された安政6年(1859年)、長男のアレクサンダー・フォン・シーボルトを伴って再来日を果たします。アレクサンダーは在日英国公使館の通訳を勤め、明治になってもお雇い外国人として40年間つとめ、明治27年の「日英通商航海条約」締結(「日英修好通商条約」の改定。列強とのと初の平等条約)にも功績がありました。次男のハインリヒ・フォン・シーボルトも明治2年に来日し、外交官として活躍。考古学にも造詣が深く、大森貝塚発見に
前述のハリスが米国の初代駐日総領事に着任したのが、黒船来航の3年後の安政3年(1856年)。ハリスが将軍(13代将軍・徳川家定、14代将軍・徳川
オールコック |
パークス |
ワーグマン |
英国のオールコックが初代公使に着任したのが翌安政6年(1859年)、オールコックから引き継いで慶応元年(1856年)パークスが公使になります。オールコックとパークスの元で通訳・書記官として活躍したのがアーネスト・サトウです。パークスとサトウは、慶応4年(1868年)の江戸城の無血明け渡しでも大きな役割を果たしました。オールコックと来日した画家のワーグマン(28歳)は、水戸浪士によるイギリス公使館(東禅寺)襲撃事件や日本の習俗などを描写。文久2年(1862年)、居留外国人向けの漫画雑誌「ジャパン・パンチ」を創刊しました(日本で最初に創刊された漫画雑誌。明治20年まで刊行)。
安政6年(1859年)ロシアのムラヴィヨフが7艘の軍艦で来航のおり、無知な攘夷派が乗組員2名を殺害しました。
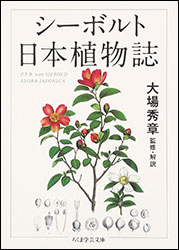 |
 |
| 『シーボルト 日本植物誌 (ちくま学芸文庫) 』。監修・解説:大場秀章。オランダ商館の医師だったシーボルトは、植物にも深い関心を寄せた | 『ヒュースケン 日本日記 〜1855-61〜 (岩波文庫) 』。ヒュースケンはハリスの秘書兼通訳を務めたが、万延元年(1861年)、攘夷派に斬殺される |
 |
 |
| 『ワーグマン日本素描集 (岩波文庫)』。編:清水 勲。ワーグマンは日本人女性と結婚し、日本で没した大の親日派。時にはリアルに時にはユーモラスに日本の諸相を描く | 『F.ベアト写真集 1 (新装版)』(明石書店)。編:横浜開港資料館。 ギリシャ生まれの写真家・フェリーチェ・ベアトも |
■ 馬込文学マラソン:
・子母沢 寛の『勝 海舟』を読む→
■ 参考文献:
●『大田区史年表』 (監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行) P.384-386、P.390 ●『詳説 日本史研究』(編集:佐藤
※当ページの最終修正年月日
2024.11.4