| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
左も右も大田南畝! ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:『近世名家肖像図鑑』(<伝>
文化5年12月16日(1808年。
、
この日は大森村で宇田川橋、土橋、石橋の修復状況を視察。翌日以降は、堤防の破損状態や六郷用水の取水口 (現在の東京都
南畝の『調布日記』(Amazon→)には、当地(東京都大田区)に滞在した翌年4月2日(文化6年(1809年))までの約3ヶ月半のことが記されています。 南畝の多摩川周辺の視察は、幕府から高く評価されたとのこと。
大田南畝でピンとこない方でも、
松平定信の「寛政の改革」を批判した狂歌、
世の中に蚊ほどうるさきものはなし
ぶんぶといひて夜もねられず
白河の清きに魚のすみかねて
もとの濁りの田沼こひしき
の2首は、南畝(蜀山人)が作ったとされてきました(異説あり。南畝も否定、肯定してたらヤバかった?)。1首目は「文武(ぶんぶ)(学芸に励め、武道に励め)と、うるせえなぁ」で、2首目は質素倹約・朱子学以外の学問禁止、と世の中をあまり「清く」したら中の魚が死んじゃうよ、悪い政治を行ったとされる田沼意次の時代が懐かしいよというもの。南畝ならこのくらいは作っただろうと疑いをかけられたようです。南畝でなくとも相当な作り手によるものですね。
 |
南畝は、寛延2年(1749年)、江戸の
大田家は代々幕府の
芭蕉の「はつしぐれ猿も
俳諧の猿の小蓑もこの
狂歌衣をほしげなりけり
と、恐れ多くも俳聖(芭蕉)も料理しちゃっています!
天明6年(1786年)、10代将軍・徳川
危機一髪の南畝は、敵の懐に飛び込むがごとく、松平定信が始めた登用試験に応募し(寛政6年(1794年)。南畝45歳)、首席で合格。文政6年(1823年)に74歳で死去するまでの20年間は、(真面目に?)幕吏として生きています。冒頭で紹介した文化5年(1808年。59歳)の多摩川の巡視はその期間に属します。
南畝には、
世の中にたえて女のなかりせば
をとこの心はのどけからまし
とか、南畝の作でないとの意見もあるようですが、
冥途から今にも使が来たりなば
九十九迄は留守とこたへよ
辞世の歌も、
今までは人のことだと思ふたに
俺が死ぬとはこいつはたまらん
と、その期に及んでですから、やはり凄いです(南畝の歌でないとの説もあり)。
 |
 |
| 手造り肉まんの店「フル オン ザ ヒル」の店先のベンチで美味しい肉まんをいただきながら、南畝(資料が展示されていた) | 「フル オン ザ ヒル」から外堀通りに出てJR「御茶ノ水」駅へ。駅の皇居側近くに、南畝終焉の地の案内板がある |
勝 海舟は6〜7歳頃、伯父の家で“蜀山人”によく会ったそうですが、蜀山人は勝が生まれた文政6年(1823年)に亡くなっており(勝が生まれたのが1月30日で、南畝が死んだのが4月6日なので、2ヶ月ほど重なっている)、勝が会ったのは2代目蜀山人(亀屋
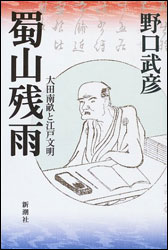 |
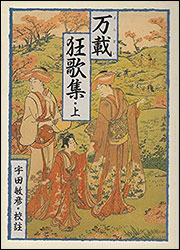 |
| 野口武彦『蜀山残雨 〜大田南畝と江戸文明〜』(新潮社) | 『 |
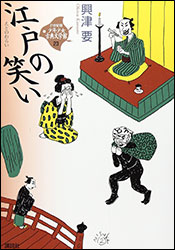 |
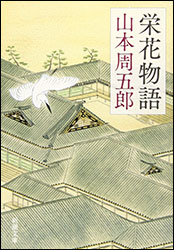 |
| 興津 要『江戸の笑い (21世紀版・少年少女古典文学館 第23巻) 』(講談社) | 山本周五郎『栄花物語 (新潮文庫)』。田沼意次は本当に“悪者”だったのか? |
■ 馬込文学マラソン:
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
■ 参考文献:
●『大田区史年表』(監修:新倉善之 東京都大田区 昭和54年発行)P.343-345 ●『大田区の史跡散歩(東京史跡ガイド11)』(新倉善之 学生社 昭和53年発行)P.100-104 ●『蜀山人全集(第1巻)』(吉川弘文館 明治40年発行 NDL→)P.271、P.275 ※『調布日記』を収録 ●『蜀山残雨 〜大田南畝と江戸文明〜』(野口武彦 新潮社 平成15年発行)P.10-12、P.25、P.79、P.249 ●『江戸文人おもしろ史話』(杉田幸三 毎日新聞社 平成5年発行)P.68-72 ●「玉川と治水/幕府の河川支配と改修工事」(佐々悦久)P.523 ※『大田区史(中)』(東京都大田区 平成4年発行)に収録 ●『江戸から東京へ(八) 〜小石川〜(中公文庫)』(矢田挿雲 昭和50年発行)P.318-319 ●『氷川清話(講談社学術文庫)』(勝 海舟 平成12年初版発行 平成27年発行40刷)P.305-306
※当ページの最終修正年月日
2023.12.16