| {column0} |

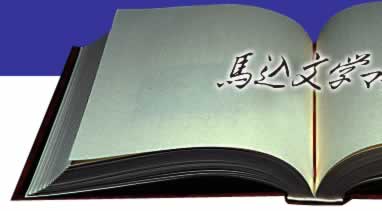







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
人物は中国の戦場でメモをとる火野葦平。彼の戦後は・・・ ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典: 『河童憂愁 〜葦平と昭和史の時空』(西日本新聞社)
 |
昭和35年1月30日(1960年。
火野
火野の死因は当初心筋梗塞と公表されましたが、12年経った昭和47年、13回忌のおりに、自死であったことが遺族によって明かされました。
昭和13年火野(38歳)は、間宮茂輔の『あらがね』を破って、『糞尿譚』で第6回芥川賞を受賞。出征中だった火野は、出征先で賞を受賞、大きな話題になります。その話題性に目をつけた陸軍は火野を説得して陸軍の報道班員に仕立てあげました(タイトル下のビジュアルの人物の腕章に注目)。同年(昭和13年)に発行された『麦と兵隊』(Amazon→)が大ベストセラーになります。火野は、日本による中国侵略戦争(日中戦争)からアジア太平洋戦争にかけ、上海、南京、杭州、徐州、広東、海南島、マニア(フィリピン)、バターン半島(フィリピン。「死の行進」も目撃)、インパール(インド)、雲南(中国)と戦場を駆け巡り、多くのメモと作品を残しました。彼ほど長期間にわたって戦場に立ち続けた作家は日本にはいないとのこと。
戦中「大東亜共栄圏」に幻想を抱き、ことあるごとにその宣伝し徹した火野は、戦争推進者として、戦後、激しいバッシングを受けることとなります。戦中「(火野に)くっついていた者」までが
しかし、死去した昭和35年ごろには、月に500枚をこなすほどの多忙な日々になっていました(昭和25年火野43歳、公職追放解除)。自他ともに認める豪胆な性格で、若い頃からの無理がたたってか、高血圧と眼底出血の症状が出始めます。『革命前後』は死を覚悟した火野が、残る生命を全投入して書いたものなのでしょう。
『革命前後』の舞台は火野の故郷の福岡で(福岡県若松)、敗戦直前から昭和22年にかけての火野自身を投影した作家「辻 昌介」が主人公です。この作品で、火野は自身の戦争責任を徹底的に追求しました。主人公の辻に以下のように語らせています。
・・・自分は一体、なにものであろうか。恐らく一人の馬鹿なのであろう。死ぬ価値があるだろうか。ただ祖国の勝利を願って、がむしゃらにやって来た。戦意昂揚とか、宣伝扇動とかにありたけの力を傾けた。・・・(火野葦平『革命前後』より)
敗戦を境に多くの人があたかも自分は戦前戦中から戦争に反対だったようなそぶりをするようになりましたが、火野はそこに逃げませんでした。「作家として、人間として、日本人として、どうしても作品に書かなければいけないと思いつづけてきた」ことを書き、その完成に大喜びし、安堵し、そして、自ら死に赴いたのです。外部からの戦争責任論は数多くあるでしょうが、内部からのそれは数が限られ(あったとしても自己弁護的であったりして)、貴重なものです。
・・・私はこの『革命前後』の最後の行を書いてペンをおいたとき、涙があふれて来てとまらなかったことを、恥かしいけれども告白します。奇妙なことに、フィナーレは、墓場で仲間たちがゲラゲラ笑う場面であるのに、それを書く私の方は泣いてしまいました。・・・(火野葦平『革命前後』の後書より)
なお書名に「革命」とあるのは、敗戦当初、多くの日本人が自由と民主主義とが日本にもたらされると実感したからで、つまりは近々そういった革命が成就するだろうと実感していたからです。
 |
蓮田善明 |
同じ戦後の自死でも、文学者(国文学研究者)・
火野にしても蓮田にしても、“御国のため”に尽くし、戦後、死んでいきました。
では、“御国のため”という大義名分で、自由主義者や社会主義者(共産主義者を含む)や民主主義者を中心になって弾圧し、その多くを死に追いやった特別高等警察(特高)の人たちは、どういった自責の戦後を送ったでしょう?
驚きました。特高官僚の多くが、国会議員、国家機関や地方自治体の要職について悠々たる戦後を送っているではないですか! そのポストたるや、国家公安委員、警察庁長官、警視総監、防衛事務次官、自治事務次官、文部事務次官、厚生事務次官、公安調査庁局長、県知事、副知事、市長、助役、教育委員長などと
 |
 |
森戸辰男 |
昭和12年言論弾圧により東京帝国大学を追われた矢内原忠雄は、戦後、東京大学総長に迎えられ、同じく東京帝国大学を追われた森戸辰男は戦後、広島大学の学長に迎えられました。森戸は文部大臣にも起用され(芦田 均内閣)、日本の朝鮮政策によって生み出された在日朝鮮人に対して温情ある政策を推進しました(その後の大達茂雄(吉田 茂内閣)がひっくり返してしまうが)。
戦後の小津安二郎監督は、帰還した男たちの孤独(戦場に行かなかった人々にはおそらく理解しえなかったであろうあれこれを抱え込んだ男たちの孤独)をさりげなく描いています。
 |
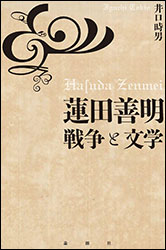 |
| 火野葦平『革命前後(上巻)(火野葦平戦争文学選第6巻)』(社会批評社) | 井口時男『蓮田善明 戦争と文学』(論創社)。“蓮田善明”という禁忌に触れる |
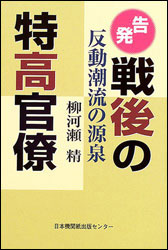 |
 |
|
|
|
■ 馬込文学マラソン:
・間宮茂輔の『あらがね』を読む→
・三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『鶴島正男聞書 河童憂愁 〜葦平と昭和史の時空』(城戸 洋 西日本新聞社 平成6年発行)P.230-235 ●『戦場で書く 〜火野葦平のふたつの戦場(朝日文庫)』(渡辺 考 朝日新聞出版 令和2年発行)P.13-15、P.24、P.328-330、P.364-366 ●『蓮田善明 戦争と文学』(井口時男 論創社 平成31年発行)P.11-16、P.318 ●『告発 戦後の特高官僚 〜反動潮流の源泉〜』(柳河瀬 精 ( やながせ・ただし ) 日本機関紙出版センター 平成17年初版発行 平成29年発行2刷参照)P.11
※当ページの最終修正年月日
2023.1.30