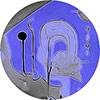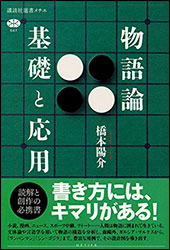大正11年3月15日(1922年。
芥川龍之介(30歳)の作品集『将軍』が発行されました。
「将軍」「羅生門」「鼻」「猿」「運」「薮の中」「手巾」「虱」「秋」の9篇が収録されていますが、そのうちの4篇(「羅生門」「鼻」「運」「薮の中」)は、平安後期(1100年代初期)に成立したとされる説話集『今昔物語集』から材が取られています。
『今昔物語集』は、全31巻。現在は3巻を欠き、説話の一部が欠けているものも少なくありませんが、全部そろっていたら1,200を超える説話が収録されていたとされます。日本最大の説話集です。
収録されている説話(物語)は「天竺(インド)」物、「震旦(中国)」物、「本朝(日本)」物に大別され、本朝物だと日本各地の地名が登場、当時の60余州のうち登場しないのは3州のみ(壱岐、対馬、石見)とのことです。
登場するのは、皇族・貴族、受領
、武士、僧侶、豪族、医者、学者、技術者、魚農工商の庶民、当時賎民とされいていた人々、さらには、神仏、妖怪変化、動植物まで。
「羅生門」(青空文庫→)は、主に『今昔物語集』第29巻18話の「羅城門の上層に登りて死人を見る盗人
の物語」(現代語訳→)に基づいています。羅城門の上層で死人の髪を抜いている老婆を目撃した盗人が、そのおぞましさに恐怖しつつも、老婆の服だけでなく死人の服、さらには老婆が抜きとった髪さえも奪って逃走するという同情の余地のない話です。それを芥川は、餓死するか盗むかの二者択一に迫られた時の心理、悪の正当化がもう一つの悪を生んでいく心の機微を捉えた作品に生まれ変わらせています。いうまでもなく文学性は芥川作品の方が断然高いですが、今昔物語の手加減のない人間描写が元にあってのこそでしょう。共に、陶冶されていない人間が「自分が生きるためだったら人から奪う存在」に簡単に転落するといった「略奪譚」(「悪行譚」の一つ)。略奪譚は、歴史や生活に中でも、繰り返し、繰り返し再生されてますね(日本のアジア侵略→ 米国の北米侵略→)。
芥川の「鼻」(青空文庫→)は、主に『今昔物語集』第28巻20話の「池尾の禅珍内供の鼻の物語」(現代語訳→)に基づいています。高僧・禅珍の顎
の下まで垂れ下がった長い鼻を持ち上げる役の子どもがくしゃみした瞬間、鼻がお椀に落ち、お粥が飛び散って、禅珍は激怒。禅珍の叱り文句に弟子たちが爆笑するという「滑稽譚」(「世俗譚」の一つ)です。身分のある人が、威厳を保つために、取り繕って、それが皆の笑いを誘うという話は落語にもよくありますね(「
転失気」「千早ふる」「味噌豆」など)。それを芥川は、人と違っている所を苦にする心理、また、苦にしていることを人に気取られたくない心理、さらには、人が好調になることをどこか嘲笑いたくなる傍観者の下卑た心理にまで拡大して物語を作り変えています。
芥川の「運」(青空文庫→)は、主に『今昔物語集』第16巻33話の「貧しき女が清水の観音に仕え盗人の夫に値
う物語」(現代語訳→)に基づいています。清水の観音に熱心にお参りしていた貧しい女が裕福な男に出会うが、その男が盗人だったという「応報譚」です。それを芥川は、青侍と陶器師の会話の中に落とし込み、2つの価値観を屹立させます。女は、盗人が捕まった後も、盗品の見張りをしていた老婆を殺してしまった後も、盗人からもらっていた盗品の品々を元手にして幸せに暮らしていけるのですが、女に果たして「運」が向いたのか否か(観音の利益があったのか否か)と考えさせます。青侍には、
「とにかく、その女は仕合せ者だよ」
と語らせ、陶器師には、
「手前ですか。手前なら、そういう運はまつぴらですな」
と語らせています。
おそらく人間には、「結果オーライ」の人間と、「プロセスこそが大切」の人間が、言葉を変えれば、芸術(真実)をおざなりにする人間と、大切にする人間とがいるのでしょう。
芥川は、こういったあまり言及されない作品(「運」)の中でも、きっちりと問題提起しているのですね。
以上紹介した3作品(「羅生門」「鼻」「運」)は、実は、5年も前に発行された作品集『羅生門』にすでに収録されたものですが(大正6年、芥川25歳。「羅生門」の初出は大正4年(芥川23歳)、「鼻」の初出は大正5年(芥川23歳。この作品が夏目漱石から激賞されて芥川は文壇に登場))、「藪の中」だけは、作品集『将軍』が発行されたのと同じ大正11年に初出されたものです。他の作品とは5年以上の開きがあり、この間の芥川の成長が読み取れます。ダントツに面白く、スリリングで、意外な展開も用意されています。なおかつ(実はここが一番重要)、深い人間洞察と、問題提起がなされています。
芥川の「藪の中」(青空文庫→)は、主に『今昔物語集』第29巻23話の「妻を具して丹波の国に行く男、大江山において縛られし物語」(現代語訳→)に基づいています。夫婦が妻の実家への旅の途上、太刀を持った屈強な若い男に出会います。男は夫を騙して弓具一式を奪い、夫を木に縛りつけて、夫の目の前で妻を犯します。男が去った後、妻は頼りない夫を詰る。物語の話者も夫の情けなさと愚かさを批判、男の方は女の着物だけは残していったのだから立派だと褒めています・・・。すさまじくドライな話ですね! こういった“野獣味”が「今昔物語」の魅力なのでしょう。「武士勢力の勃興」(“力”崇拝)の影響もあったことでしょう。
それを芥川は「藪の中」で、冒頭に藪の中の男の死体を出し、それについての7人の証言を重ねていく形で物語を展開していきます。第一発見者の木樵り、前の日に男に会った旅法師、犯人らしき盗人を捕らえた人、男の義母、犯人らしき盗人、男の妻、とそれらの証言から事件の真相が徐々に明らかになっていきます。これは「寝取られ譚」の一つですが、悲惨なのは、それが夫の目の前で行われたこと。「今昔物語」では、寝取られた男が全く同情されませんが、「藪の中」では、ことのあった後に、妻が夫の目の中に「怒りでもなければ悲しみでもない、──唯わたしを蔑んだ、冷たい光」を認めることで、一層悲劇的なものになっていきます。
ここまででも十分に面白いのですが、極め付けは7人目の証言です。7人目の証言者は何と「巫女
の口を借りたる死霊」です。つまりは死んだ男の証言が始まるのです! 果たして、男に止めを刺したのは誰でしょう?
芥川の物語の作り直しは見事です。
 |
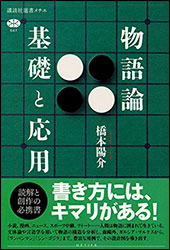 |
| 『今昔物語集 本朝部 上(岩波文庫)』。編:池上洵一 |
橋本陽介『物語論 〜基礎と応用〜』(講談社) |
 |
 |
| 芥川龍之介『藪の中(講談社文庫)』。表題作の他、「羅生門」「地獄変」「蜘蛛の糸」など6編を収録 |
『羅生門」。原作:芥川龍之介の「藪の中」。監督:黒澤 明。ヴェネツィア映画祭で金獅子賞を受賞 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 芥川龍之介の『魔術』を読む→
■ 参考文献:
●『今昔物語』(長野甞一
)※『新潮 日本文学小辞典』(昭和43年初版発行 昭和51年発行6版)に収録 ●「日本の古典を題材にした芥川龍之介の作品」(岡山県立岡山芳泉高等学校図書館)(PDF→) ●「芥川龍之介略年譜」(関口安義)※『芥川龍之介(新潮日本文学アルバム』(昭和58年初版発行 同年発行2刷)に収録
※当ページの最終修正年月日
2025.3.11
この頁の頭に戻る
|