| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和4年12月15日(1929年。 、松竹蒲田撮影所の斎藤寅次郎監督(24歳)の映画「全部精神異常あり」が封切られました。
米国で大ヒットした反戦映画「西部戦線異常なし」の日本上映が決まって宣伝され始めたころで、それをもじったタイトルになっています。浅草で両作が向かい合って上映されたところ(映画の町・浅草の黄金期で、映画館が軒を連ねた)、「西部戦線異常なし」を見るために来た客が、「全部精神異常あり」を上映している映画館の方に間違って入ってしまうということもあったとか(笑)。
「全部精神異常あり」で描かれたのは、“全てがあべこべの世界”です。
踏切は電車が通過するのを通行者が待つものと決まっていますが、「異常あり」では牛車が通るのを汽車が待ちます。汽車から降りてきた山高帽にフロックコートの紳士が駅前で人力車に近づくと、車夫が座席にでんと座り紳士が車を引く。宿に着くと紳士は働かされて、寝るのは犬小屋。なんと犬が座敷に寝る・・・。まだまだ続いて、宿の主人の息子が車で人をはねてしまいますが、息子は人をはねてしまったショックで死亡、はねられた人はぴんぴんしています。死亡した息子の親(宿屋の主人)に保険金が下りますが、彼はなんと「札束恐怖症」。札束を見て逃げ出す始末。買物すると金がもらえ、雨が止んで開く傘、風呂には服を着て入り、裸で出る・・・。と、ハチャメチャです。が、「“普通の世の中”のおかしさ」もあぶり出しているようです。主演は星 光(ひかる)で、その他、突貫小僧(青木富夫)、坂本 武、吉川満子も出ます。 斎藤監督は、蒲田時代、こういった先鋭的な喜劇をずいぶん撮ったようです。
残念ながら斎藤監督の蒲田時代の作品はほとんど失われ(「全部精神異常あり」のフィルムも見つからないようだ)、発見されているのは「石川
「石川五右衛門の法事」がYouTubeにアップされていました。
| 無一文の石川五郎は古物商・古谷の娘と恋仲だが、古谷は結婚を許さず五郎を殺してしまう。五郎は幽霊になって騒動を起こす。途中、五郎の祖先の石川五右衛の幽霊も現れて、2人の恋を実らせて、メデタシ、メデタシ。五郎を「マダムと女 房」で主演した渡辺 篤、古谷を小津映画でも大活躍の坂本 武、石川五右衛門を「マダムと女房」の冒頭に出てくる画家を演じた横尾
|
斎藤監督の蒲田時代の映画タイトルを拾うと、「全部精神異常あり」もそうですが名作のタイトルをもじった「何が彼女を裸にしたか」(大ヒット映画「何が彼女をそうさせたか」のギャグ)、「ああ無情」(レ・ミゼラブル)をもじった「
 |
 |
| 「チャップリンよなぜ泣くか」(昭和7年)の一場面。和製チャップリンとして活躍したのが小倉 繁 ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:『日本の喜劇王 〜斎藤寅次郎自伝〜』(清流出版) | 「あわてものの熊さん」(昭和8年)も斎藤映画。幽霊役は山田長正(むろん山田長政ではない) ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:『あ丶活動大写真 』(朝日新聞社) |
斎藤の映画との関わりは、10歳のころ、活動写真(映画のこと)の巡業の旗持ちを志願したことから始まります。当地(東京都大田区)にあった松竹蒲田撮影所(開所4年目)に監督志望で入社したのが、関東大震災のあった大正12年です(18歳)。撮影所が神奈川県大船に移転した翌年(昭和12年)、東宝に移籍。その後も喜劇路線を貫き、エノケン(榎本健一。浅草の「カジノ・フォーリー」の創設者の一人)、ロッパ(古川
松竹蒲田撮影所を舞台にした映画「キネマの天地」に、異常に明るい監督が出てきますが、あれが斎藤監督です(映画では内藤監督。演:堺 正章)。
「男はつらいよ」(監督:山田洋次)の主人公を寅さん(車 寅次郎)にしたのは、斎藤監督(斎藤寅次郎)へのリスペクトからでしょうが、寅さん人気が高まってきた頃、斎藤は寅次郎から本名の寅二郎に戻しています(昭和47年斎藤67歳)。“寅次郎”を寅さんに譲ったようです。
笑いは、「決まりきって、つまらなく、機械的な状態」を解きほぐす効果があるようです。「決まりきって、つまらなく、機械的な状態」を強制してくるのは、大概、政治家や親や教師や上司やその他の“えらい”とされる人たちなので、笑いの矛先がそれらの人に向かうのが健全ですね。落語でも、長老づらの「隠居」「店の旦那」「先生」「父親」「和尚」「大家」が見栄をはって、後でずっこける話によく出くわします。
昭和37年頃からの2年間ほど旋風を巻き起こした芸術集団「ハイレッド・センター」が起訴されて被告になった時、彼らは自分たちがやっていることが「芸術」であることを説明するために法廷に様々な「作品」を持ち込みました。「作品」を紹介する段になり、メンバーが丸めてあった作品を下に広げると、ペロリと「等身大の制服のお巡りさんの青写真」が現れました。厳粛であるべき廷内が、止めようもなく大爆笑になったそうです(裁判長も笑ってしまったのでは?)。ちなみに「ハイレッド・センター」の「ハイ」は
ところが、いつの頃からか、そうでない人(強制者でない人)を笑いの対象にし始めて(たけしの「ブス」ネタあたりから?)、笑いが変質したようです。人が貶められることで、ちょっぴり救われた気になる(スカッとする)、卑しい笑いですね。そういった屈折した笑いがTVにあふれ、日本特有のいじめ現象にも強い影響を与えたことでしょう。そういった面白くもないネタにスタジオのスタッフが「笑ってあげて」盛り上げる嘘っぽいやり方も不快。
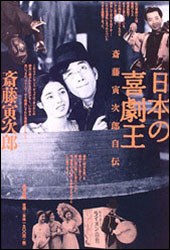 |
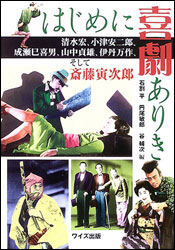 |
| 『日本の喜劇王 ~斎藤寅次郎自伝~』(清流出版)。自作を語ったエッセイ、「斎藤組の懐刀」大貫正義へのインタビューも収録 | 『はじめに喜劇ありき ~清水 宏、小津安二郎、成瀬巳喜男、山中貞雄、伊丹万作、そして斎藤寅次郎』(ワイズ出版)。編集:石割平ほか |
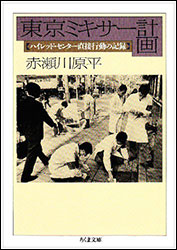 |
 |
| 赤瀬川原平『東京ミキサー計画 〜ハイレッド・センター直接行動の記録 〜(ちくま文庫)』。オリンピック一色に染まりつつある東京を撹拌する | ベルクソン『笑い(岩波文庫)』。訳:林 達夫。決まり切ったことを強制してくる空気を笑い飛ばして、個々人の生き生きとした生を守る |
■ 参考文献:
●『日本の喜劇王 〜斎藤寅次郎自伝〜』(清流出版 平成17年発行)P.8、P.19、P.43-44、P.66-68、P.139、P.216 ●『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.183-185 ●『東京ミキサー計画 〜ハイレッド・センターの直接行動の記録〜(ちくま文庫)』(赤瀬川原平 平成6年初版発行 平成19年2刷)P.274-285
※当ページの最終修正年月日
2024.12.15