| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
映画「母」の一場面。高峰秀子が子役で鮮烈デビューした ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:『わたしの渡世日記』(高峰秀子)
昭和4年11月28日(1929年。
、野村
松竹蒲田撮影所の所長・
面白くないのは、撮影所でこれまでの繁栄を築いてきた古株たちです。不満分子の最右翼が野村監督でした。彼はトーキーなどはやらぬと啖呵を切り、古株をふんだんに使う企画を城戸に叩き付けました。それが「母」です。
城戸が目指した明るい「蒲田調映画」ではなく、観客の涙を絞りに絞ろうという「ハンカチ映画」。主役の母役には、城戸推薦の新人・川崎弘子(17歳)ではなく、城戸が所長に就任してから出番を少なくしていた撮影所創設時からの名優・川田芳子(34歳)を起用しました。
映画「母」は、夫に死なれて2人の子どもを抱えて苦労する母親の物語。試写後、城戸所長は野村監督に一言「面白くありませんね」と言い、笑いながら試写室を出て行ったそうです。その一言で、野村は、撮影所を去る決意をします。ところが、「母」が大ヒット! 45日間という興行記録を作り、野村監督は去るに去れなくなりました。
 |
「母」で特筆すべきは、約60人の応募者から選ばれた子役。後のデコちゃん、こと高峰秀子(5歳)です。高峰の家族は東京鶯谷で二階借りをしていましたが、階下の家主の友人が蒲田の俳優の野寺正一(43歳)で、その関係で養父に連れられて選考に飛び入りで参加。そうしたところ、白羽の矢が立ったのでした。高峰のあまりの可愛さに日本中がニコニコになったのでしょう。以後“天才子役”として、五所平之助、島津
 |
| 映画「母」の一場面。左より、高峰秀子、川田芳子、小藤田正一 ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:『わたしの渡世日記(上)』(高峰秀子) |
高峰の“通勤”の便を考えて、家族は当地(東京都大田区北蒲田 Map→)に越してきます。撮影はざらに深夜にまでわたり、高峰は、蒲田尋常高等小学校(現・大田区立蒲田小学校(東京都大田区蒲田一丁目30-1 Map→)に在籍しますが、通えるのは月に3~4日ほど。出席しても授業には全くついていけませんでした。1~2年の時の指田という先生は、高峰が地方ロケに出発する際、駆けつけてきて、子ども用の雑誌を2〜3冊差し入れてくれたそうです。高峰はそれで文字を覚えました。後年回想して「指田先生を思うとき、感謝とか恩人とか、そんな言葉ではとうてい表現できない、胸に溢れてくる得体の知れない感情に、思わず、あれはやっぱり神様だったと手を合わせたくなる」と書いています。
高峰が当地にいたのは、昭和12年(13歳)、松竹から東宝へ移籍するまでの約7年間。途中、歌手の
子役として一世を風靡した高峰でしたが、子役について後年こんな風に書いています。
・・・映画やテレビで、ジャリタレという虫ずの走るような呼び名を与えられた
当時の私のような陰湿さもみえず、彼らは彼らなりに、それこそ何もかも承知の上で、演技をすることに嬉々としているのかもしれないが、私の眼から見れば、どうしても「大人に作られたコマッシャクれた人造子供」である。子供はいずれ成長すればイヤでも大人になる。せめて子供のときくらいは、自然な子供の世界で、子供らしく遊ばせ、子供同士の会話を持たせてやって欲しいと私は願う。仕事で子役と付きあうたびに、その子役が上手ければ上手いほど、私は「この子はいま何を考えているのだろう」と心が震えてならない。・・・(高峰秀子『わたしの渡世日記』より)
さんざん苦労してきた人の言葉には、説得力があります。
 |
突貫小僧 |
子役といえば、松竹蒲田撮影所には、“突貫小僧”もいました。「かわいい」高峰とは違って、見るからに「悪ガキ」(笑)。映画「母」と同じ昭和4年11月に公開された小津安二郎監督の「突貫小僧」に出て人気を博し、本名は青木富夫ですが、子役時代はずっと“突貫小僧”と呼ばれました。
横浜の実家が営む酒場に蒲田の俳優が出入りしていた縁で、“突貫小僧”は松竹蒲田撮影所に遊びに来るようになり、小津安二郎に見出されたようです。“突貫小僧”が出演した小津の「生まれてはみたけれど」(昭和7年)、「出来ごころ」(昭和8年)、「浮草物語」(昭和9年)はどれもキネマ旬報ベスト・テンの第1位。一人の監督が3年連続で1位の記録は今もやぶられていないとのこと。“突貫小僧”が果たした役割も小さくなかったことでしょう。
 |
| 映画「突貫小僧」の一場面。左より、斎藤達雄、突貫小僧(青木富夫)、坂本 武 ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:『あゝ活動大写真 〜グラフ日本映画史(戦前編)』(朝日新聞社) |
“突貫小僧”が、高峰について、
・・・高峰秀子は、ほかの女の子役とは違う。女の子役に見られる
と言っています。“突貫小僧”から見ても、高峰は一種の“天才”だったのでしょう。
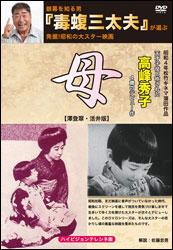 |
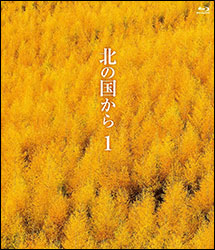 |
| 映画「母」(松竹)。監督:野村芳亭。高峰秀子のデビュー作。昭和4年、5歳 | ドラマ「北の国から 1」。子らの長期にわたる成長譚。純(小学校4年。演:吉岡秀隆)と、蛍(小学校2年生。演:中嶋朋子) |
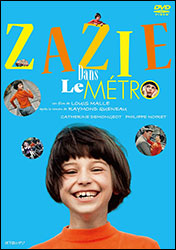 |
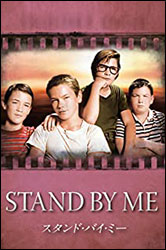 |
| 「地下鉄のザジ」。地下鉄のストライキで混乱するパリでの、少女ザジ(演:カトリーヌ・ドモンジョ)の大冒険。監督:ルイ・マル | 映画「スタンド・バイ・ミー」。12歳4人組の2日間の冒険。子どもたちも傷を抱え必死に生きている |
■ 参考文献:
●『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.169-171 ●『わたしの渡世日記(上)(文春文庫)』(高峰秀子 平成10年初版発行 平成23年発行12刷)P.34-188 ●「わが町あれこれ 5号」 (城戸 昇編・発行 平成7年発行)P.46-47 ●「高峰秀子の旅と本棚(「芸術新潮」没後一周年特集)」(平成23年12月号)P.20、P.52-53
※当ページの最終修正年月日
2024.11.28