| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
「生まれてはみたけれど」の一場面。左から斎藤達雄、突貫小僧、菅原秀雄 ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用
 |
昭和7年6月3日(1932年。 小津安二郎監督(28歳)の蒲田映画(松竹蒲田撮影所で作られた映画)「生れてはみたけれど」(Amazon→)(YouTube→)が公開されました。
小津はこの映画で初めてキネマ旬報ベスト・テンの1位を獲得。以後3年連続で1位を取って、名声を不動のものにしました。これらは、サイレント期の日本映画を代表する作品です。
父親の仕事の都合で郊外に越して来た家族の物語です。兄と弟と近所の子どもたちで作る「子どもの世界」と、父の仕事上の「大人の世界」とがぶつかり合います。兄弟は近所の金持ち息子を子分にしますが、自分たちにとって威厳ある父が、その金持ち息子の父の部下なのでした。ある日、兄弟は、父が、金持ち息子の父にこびへつらっている姿を目撃。ショックを受け、父に失望、ハンガーストライキに突入します。
ハンガーストライキで腹を空かせる兄弟が、母(演:吉川満子)がそっと置く塩むすびをチラチラ見て、我慢できずに口に入れる場面があります。意地を張る兄弟でしたが、そこに
塩むすびはどんな味だったでしょう? 父には子どもたちの気持ちに思いを巡らしちょっぴり苦い、兄弟にも父の立場に思い至りやはりちょっぴり苦い、そんな味だったでしょうか。ともあれ、和解の塩むすびでした。
 |
 |
| 兄弟はハンガーストライキに突入 | 父に言われて塩むすびを持ってくる母 |
黒澤 明監督の映画「赤ひげ」(Amazon→)にも、塩むすびの印象的な場面がありました。“赤ひげ”とは、荒くれだけれどもどん底の患者たちに常に温かい視線をそそぐ医師・
 |
 |
| 食べたくてしようがないのに、手を伸ばすことができない子どもたち | 人の目がなくなって、塩むすびにむしゃぶりつく子どもたち |
食べていかなくては生きていけない存在(人間に限らず生きとし生けるもの全てですが)、それだけでもう切ないです。
西東三鬼は、食べる行為を題材に、人間存在の“かなしさ(悲しさ、哀しさ、
原爆投下後の広島を詠んで、
広島や物を食ふ時口ひらく
「物を食う時口ひらく」といえば当たり前のようですが、その当たり前の言葉から、食べる時(生命を維持しようという時)以外は口を開く気になれない広島の“地獄”が浮かんできます。口を開く気にならないというより、皆死んでしまい、生きていても瀕死の状態で、語りかける人が誰もいないのかもしれません。
「物を食う時」はその後「卵食ふ時」に直され、ずいぶんマイルドになってしまいます。 反米的な表現を警戒していた占領軍(GHQ)は俳句雑誌も検閲、三鬼の広島を詠んだ作品にも削除命令を出したというので、手直しを余儀なくされたのでしょう。三鬼は戦前は特高からマークされ、戦後は占領軍からマークされたのですね。真の表現者です。
三鬼には兄が死んだ時詠んだ句もあります。
死顔や
「うまい」林檎を、「うまいね」と言い合いながら食べる兄はもういません。
林檎は色彩の鮮やかさや甘酸っぱさからか、他の作品によく登場します。
「人並はずれて林檎を好んだ」片山に、次の歌があります。
わが側に人ゐるならねどゐるやうに
一つのりんご卓の上に置く
人多く住みける家をおもひいづ
林檎をもりし幾つもの皿
努めて考えないようにしている人も多いのでしょうが、どの人にも、いつかは必ず、様々な形で別れがやってきます。どの人も避けられません。これだけは平等です。だから、文学も必要になってくるのでしょう。
 |
小津映画「晩春」(Amazon→)のラスト。娘の婚期を気にして、自分も再婚すると嘘をついてまで(父が一人になることを気にして娘は結婚しない)、娘を結婚に追いやる父でしたが、今や一人、林檎をむく |
印象的な食べる場面がいろいろ思い浮かびます。ドラマ「冬のソナタ」(Amazon→)で悲しみのどん底のユジンがおかゆをすする場面も忘れられませんし、ドラマ「北の国から」(Amazon→)で草太とつららがラーメン屋でラーメンを食べる場面も秀逸。黙々と食べる草太と、泣き笑いしながらラーメンを食べるつらら・・・。「北の国から」には、もう一つラーメン屋での名場面がありました。シリーズのクライマックスの一つでしょう(ご覧になった方はお分かりですよね?)。
マキヒロチのコミック「いつかティファニーで朝食を」は、タイトルから予想されるように、1 SCENE(章)ごとに朝食を食べる場面があります。11 SCENE「実家と、みかんと。」(第2巻に収録 Amazon→)では、登場人物の麻里が、年末に実家に戻ると、久しぶりに会う愛犬「みかん」が年取って弱っているのでした。上着で温めながら散歩をしますが、それでもどんどん弱っていく「みかん」。そして、年が明けた頃、とうとう逝ってしまいます。正月の朝、家族でおせち料理を囲みますが・・・
食べることそのものをテーマにした伊丹映画「タンポポ」も超おすすめです。ラーメン屋を成功に導くというメインストーリーに、食にまつわる強烈かつ印象的なサブストーリーがいくつも錯綜してきます。キネマ旬報ベストテンの1位でないのがとっても不可解。まさに無冠の傑作です!
食べるの究極は「食人」。極限状況や置かれた時などに、人は、人を食うことがあります。
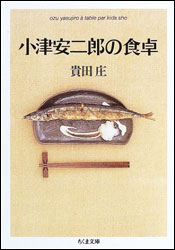 |
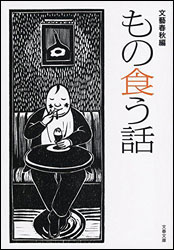 |
| 『もの食う話 (文春文庫) 』。鷗外、荷風、百閒、夢野久作、澁澤龍彦、筒井康隆、水木しげるらの「食う話」 |
 |
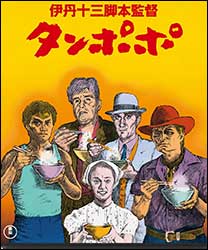 |
| 村瀬 学『「食べる」思想 ~人が食うもの・神が喰うもの~』(洋泉社)。「食べる」が支える「考える」 | 「タンポポ」。監督・脚本:伊丹十三。出演:山崎 努、宮本信子、渡部 謙、役所広司、安岡力也ほか、往年の名優もずらり |
■ 馬込文学マラソン:
・ 片山広子の『翡翠』を読む→
■ 参考文献:
●『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.167-182 ●『小津安二郎の食卓』(貴田 庄 芳賀書店 平成12年発行)P.58-59、P.175、P.195、P.202-204 ●「『食魔 谷崎潤一郎』(坂本 葵) ~文豪と味な出会いを~」(川原田喜子)※「東京新聞(朝刊)」平成28年8月7日掲載 ●「広島や卵食ふ時口ひらく(西東三鬼)」(感性創房→) ●『片山広子 ~孤高の歌人~』(清部千鶴子 短歌新聞社 平成9年初版発行 平成12年発行3刷)P.76-80、P.110-111、P.125-126
※当ページの最終修正年月日
2024.6.3