| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和24年7月19日(1949年。
三島由紀夫(24歳)が精神科医の
・・・
 |
式場隆三郎 |
式場は三島より27歳年上でこの時点で51歳。若い頃から文芸や美術にも傾倒し、精神科医の立場からゴッホ、ロートレック、ビアズリーらを考察してきました。三島は式場の本を読んできており、式場なら『仮面の告白』に表出された自身の同性愛的傾向を理解してくれるに違いないと考えたのでした。“性的倒錯”の告白的な記録は稀で、『仮面の告白』は世界的にみても先駆的だろうとの自負が三島にはありました。
平成2年までWHO(世界保健機関)のICD(疾病分類)に同性愛が載っており、同性愛は病気(“Sexual inversion(性的
精神(心)の探求が、心理学という科学として確立するのは、1800年前後に、実験的方法が取り入れられるようになってです。1879年(明治初期)、ライプツィヒ大学(ドイツ)に心理学実験室を開設したヴントが最初の心理学者とされています。実験室で条件を一定にして、知覚・情動・意識といった心的活動が測定されるようになりました。
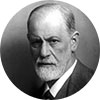 |
 |
 |
フロイト |
ユング |
アドラー |
1890年代(明治23年〜)になると、オーストリアの精神科医・フロイトが、臨床経験に基づき、精神分析を創始。性的欲望が抑圧されて神経症を発症したり、近親相関的願望がパートナーとの出会いによって克服されていったり、と普段は意識されない「無意識」の欲望や願望が、人間の行動や感情に大きく影響していることを発見。これらの知見は、人間理解(自己理解を含む)を革命的に進歩させ、精神医学に止まらず、文学や芸術にも大きな影響を与えていきます。
ユングはフロイトの影響を色濃く受けましたが、後に、神経症の主因を性的抑圧に求めるフロイトと
アドラーもフロイトの共同研究者でしたが、やはりフロイトの性欲一辺倒に疑問をもち、決別、独自の心理学を確立していきました。過去や環境に原因を求めることよりは、未来(目的)を自己決定するプロセス、劣等感を補おうとするプロセス、社会や人的環境が個人与える影響力などを重視しました。
 |
ブルトン |
フロイト以降、無意識の働きに注目しながら自他を理解し、それを表現する試みがなされてきました。過度の拒絶や神経症的な振る舞いに抑圧された無意識の欲望を読み取ったり、夢に現れるイメージから無意識の欲望や恐怖を読み取ったり。意識的な制約や道徳的な先入観から離れて、無意識の世界に“真実”(リアル)を見ようとする芸術運動・シュルレアリスムが宣言されるのが大正13年です(アンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』を発行した)。ダダイズムがそうであったように、意識だけが作り出したような既成の文化や芸術の否定です。ブルトンは精神分析のオートマティズム(意識を介在しない動作)の手法を使って、思いつくままに言葉を連ねて詩を書きました。ダリ、エルンスト、キリコ、タンギー、マグリット、エドガー・エンデ(『はてしない物語』の著者・ミヒャエル・エンデの父親)などの絵はあたかも夢の中のイメージのようです。ポロックは絵の具を
 |
 |
| イヴ・タンギー(仏、1900-1955)の「不孝が石たちを柔らげる」 ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:パブリックドメインR→ | エドガー・エンデ(独、1901-1965)の「大浪のなかの男」 ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:パブリックドメインR→ |
古今東西、詩歌で「
・・・you may know how to cut hair,
you may be somebody's mistress,
may be somebody's heir・・・
(ボブ・ディラン「Gotta serve somebody」より)
「hair」(髪の毛)と「heir」(遺産相続人)は、リズム(繰り返し)を作るためにたまたま拾われた言葉なのでしょう。
大正元年頃から日本でも精神分析が知られていきます。
フロイトは精神分析で「自由連想法」を使用しました。被試験者に刺激語を与えて自由に連想語を言わせ、刺激語と連想語の関係や、連想語を言うまでの反応時間などから、被試験者の無意識を顕在化させ、自覚させ、治療に役立てようというものです。大正14年発表の江戸川乱歩の短編『心理試験』(青空文庫→ Amazon→)では、犯人が取り調べで使われる「自由連想法」に備えて疑われようもない“完璧な連想語”を準備します。しかし、そこで、名探偵・明智小五郎が登場。D坂で初登場した明智の2番目の推理です。
心理の探求は人間探求であり、ものを書くプロセスと似ているからでしょうか、精神科医で物を書く人がけっこういます。斎藤茂吉、
現今、「
 |
|
| 「式場隆三郎 脳室反射鏡 展 図録」。八面六臂の式場の仕事を一望 |
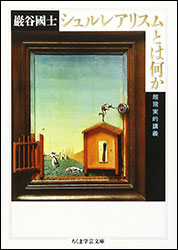 |
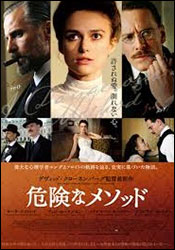 |
| 『危険なメソッド」。精神科医フロイトとユングの戦い。患者のザビーナ(後に精神分析家となる)、特異な精神科医・オットー・グロースも実在の人物とは、驚き |
■ 馬込文学マラソン:
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
・ 辻 潤の『絶望の書』を読む→
■ 参考文献:
●『決定版 三島由紀夫全集(38)』(新潮社 平成16年発行)P.513-514 ●『三島由紀夫研究年表』(安藤 武 西田書店 昭和63年発行)P.77 ●「心理学」(萩野源一)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●「ユング」(河合隼雄)※「世界大百科事典(改訂新版)」(平凡社)に収録(コトバンク→) ●「シュルレアリスム」(副田一穂)(美術手帖→) ●「オートマティズム」(刈谷洋介)※「現代美術用語辞典 1.0」(DNP→) ●「日本における黎明期の精神分析 〜大槻憲二と古澤平作の貢献〜」(中野明徳)※「福島大学総合教育研究センター紀要」(平成27年発行) (福島大学学術機関リポジトリ(PDF)→ )
※当ページの最終修正年月日
2024.7.22