| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
「看」という漢字は、「手」と「目」の会意文字。「手」を「目」にかざしている象形でもあるのだろう
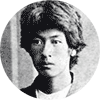 |
明治23年1月23日(1890年。
大磯の「
新島に師事していた徳富蘇峰(26歳)が新島の危篤の知らせを受けたのは3日前の1月20日。その日、蘇峰は自らが主宰する「国民新聞」 創刊の披露パーティーがありました。 大事業にこぎ出す大切な日でした。蘇峰はフロックコートで正装し、銀座の床屋で顔をそってもらっている最中だったそうです。
知らせを聞いた蘇峰は、家にとんで帰って、パーティーを人に託し、クリスチャンの新島のために牧師を手配し、大磯へ急行します。
そして、蘇峰は3日3晩徹夜で看病し、新島を看取ります。 新島が亡くなったとき、蘇峰はパーティーの正装のままの姿でした。残された新島の妻(新島八重)には、今後も付き合っていただきたいと伝え、慰めています。
じゃっかん26歳です。新聞社を立ち上げようという気概といい、新島の死にさいしてとった行動といい、やはり、並みの人ではないです。それだけにその後の変節が残念。
 |
新島の米国 |
尼僧・貞心(33歳)も、天保元年(1830年)、師の良寛(72歳)の急の知らせを聞いて、年の瀬の庵主の勤めを投げ出して、島崎(現・長岡市)の良寛の元に飛んでいき、看取ったようです。
 |
堀 辰雄の『風立ちぬ』(Amazon→ 青空文庫→)は、一種の「看取り文学」です。結核に冒された婚約者に付き添って高原のサナトリウムに入る「私」。少しずつ弱っていく彼女との愛おしい一瞬一瞬が綴られています。
・・・そんな
「何をそんなに考へてゐるの?」私の背後から節子がたうとう口を切つた。・・・(堀 辰雄『風立ちぬ』より)
長い長い看る(介護)期間には、また格別な苦労と哀歓とがあることでしょう。
文筆家の平川克美さんは、80代半ばで老老介護していた両親のうち母親が死去したのを機に、当地(東京都大田区)にある実家(千鳥町駅(Map→)と久が原駅(Map→)の中間あたりで町工場をやっておられた)に戻ったそうです。それまでまともに話をしたことがなかった父と子が、父の最後の一年半、生活をともにします。かつて毅然としていた父の心身の衰えを見るのは辛いことですが、その過程で、ともに歩んで来た道を振り返り、新たに気づくことも多かったようです。“看る(介護する)人だけが味わうことができる深い喜び”があるのを知りました。
・・・五分も湯につかっていると、父親の胸の辺りからヒューヒューと異音がしてくる。肺気腫があるので、すぐに呼吸が苦しくなってくるらしい。湯船から引っ張り上げて、持ち込んだ円椅子に座らせ、頭と身体を洗ってやる。背中がかゆいらしくて、強く洗ってくれと催促がくる。
寒いので速攻で洗うが、おむつを当てていた股間は念入りに洗う。最初はお互いに抵抗があったが、慣れてしまえばなんということもなくなる。だらりとぶら下がったイチモツを引っ張って、ごしごしと洗えるようになる。
お尻の穴に指を突っ込んで、溜まっているウンチを掻き出すこともある。これをしないと、どうしても便秘になってしまうのだ。・・・(中略)・・・思うに、股間を洗えるようになることが、介護の第一ハードルを越えることになる。
・・・(中略)・・・
「さっぱりしただろ」
「ああ、風呂はいいなぁ」
この会話を何度繰り返しただろうか。そして、この会話がどれほどの幸福感をもたらすものかを実感する。
「風呂はいいなぁ」という言葉のなかには、言葉では言い尽くせないたくさんの思いが詰まっているような気持ちがする。こういったことだけは、介護をした者だけが味わうことのできる特権である。・・・(平川克美『俺に似たひと』より)
妻に先立たれ、養子の
萩原葉子の最後の186日間を同居し最後を看取った一人息子の萩原
そういえば、横光利一の『春は馬車に乗って』(Amazon→ 青空文庫→)も「看取り文学」でした。横光は28歳のとき、23歳の妻・ミキを亡くしており、その時のことが題材になっているようです。妻はひっきりなしに
・・・「人が苦しんでいるときに、あなたは、あなたは、他のことを考えて」
「まア、静まれ、いま
「あなたが、落ちついているから、憎らしいのよ」
「俺が、今
「やかましい」
彼女は彼の持っている紙をひったくると、自分の痰を横なぐりに拭きとって彼に投げつけた。・・・(横光利一『春は馬車に乗って』より)
キレイごとですまない現実。本のタイトル“春が馬車に乗って”やって来るのにはまだ間がありそう・・・
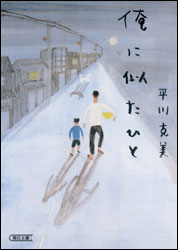 |
 |
| 平川克美 『俺に似たひと (朝日文庫)』 | 萩原朔美 『死んだら何を書いてもいいわ ~母・萩原葉子との百八十六日~』(新潮社) |
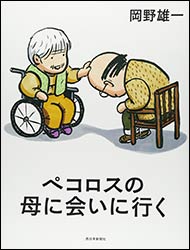 |
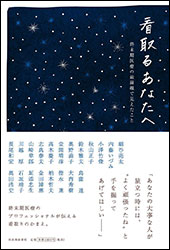 |
| 岡野雄一『ペコロスの母に会いに行く(西日本新聞社)。映画化されたものはこちら(出演:赤木春恵、岩松 了ほか)→ | 『看取るあなたへ』(河出書房新社)。徳永 進(野の花診療所)、高木慶子(たかき・よしこ。上智大学グリーフケア研究所特任所長)ほか |
■ 馬込文学マラソン:
・ 堀 辰雄の『聖家族』を読む→
・ 萩原葉子の『天上の花』を読む→
■ 参考文献:
●『蘇峰自伝』(中央公論社 昭和10年発行)P.260-262 ●『俺に似たひと』(平川克美 医学書院 平成24年発行)P.88-90 ●『死んだら何を書いてもいいわ 〜母・萩原葉子との百八十六日〜』(萩原朔美 新潮社 平成20年発行)P.104-106 ●『添田唖蝉坊・知道 ~演歌二代風狂伝~』(木村聖哉 リブロポート 昭和62年発行)P.258-265、P.284 ●「神奈川文学年表/明治21年~30年」(神奈川近代文学館→)
※当ページの最終修正年月日
2024.1.22