| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和7年公開の小津安二郎監督の映画「生れてはみたけれど」には、「池上線」の電車が何度か登場。ロケで撮影された。背後にいるお父さん役は斎藤達雄で、左の子役は菅原秀雄。右の子役は突貫小僧(青木富夫)だ ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:映画「生れてはみたけれど」(松竹)
大正6年6月24日(1917年。目黒と大森を結ぶ目的で「池上電気鉄道(株)」が設立されました。
しかし、目黒と大森を結ぶ予定が、大森の用地買収で難航、起点が目黒から五反田に変更になるなど混乱している時に、
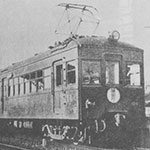 |
昭和初期の「池上線」の電車。初期の頃は、単線で、1車両だったのだろう ※「パブリックドメインの写真(根拠→)」を使用 出典:『大田区史(下巻)』(東京都大田区) |
同じ時期(大正9年)、「田園都市株式会社」も臨時総会で鉄道建設を決定し、大正11年鉄道部門が独立して「目黒蒲田電鉄(株)」が設立されます。そして、翌年(大正12年)には「目蒲線」(現在の多摩川線・目黒線)の「目黒駅」〜「丸子駅」(現「沼部駅」)間が開通します。「目蒲線」は当初、東京から多摩川や洗足池を望む分譲住宅地を目指しました。
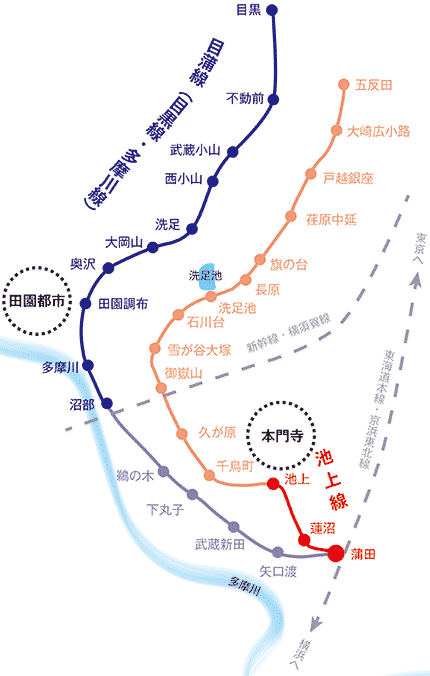 |
上図の赤い部分が「池上線」で、紺色の部分が「目蒲線」です。大正11年に開通した「池上線」の蒲田駅〜池上駅間を濃くしました。翌年(大正12年)開通した「目蒲線」の目黒駅〜丸子駅(現・沼部駅)間も濃くしました。
 |
大正15年12月、宮沢賢治が上京のおり、池上線の「千鳥町駅」(当時は「慶大グランド前駅」)近くの大津三郎(新交響楽団<現・NHK交響楽団>団員)の家にチェロを習いにきています。池上駅〜雪ヶ谷駅(現・雪が谷大塚駅)間の開通は大正12年ですが、その中間の「千鳥町駅」ができるのは同年(大正15年)8月6日です。賢治は出来たてホヤホヤの千鳥町駅に降り立ったのでしょうか。
賢治が大津の家を訪れた昭和元年の12月25日〜28日(1926年12月25日より昭和なので、賢治は昭和の最初の3日間当地(東京都大田区)を訪れたことになる!?)あたりで、その頃の「池上線」は蒲田駅から雪ヶ谷駅(現・雪が谷大塚駅)までしか通じていませんでしたが、翌年(昭和2年)には大崎広小路駅まで通じます。ちょうどその頃、新響(新交響楽団)の練習場が荏原(荏原中延駅あたりか)に建設中で(賢治が大津の家を訪れた大正15年・昭和元年12月に地鎮祭があった)、それを踏まえ、練習場への便を考えて大津は千鳥町に屋敷を構えたのかもしれません。千鳥町駅から荏原中延駅までは現在の「池上線」の駅で8つ目です。「池上線」は駅と駅の間隔が狭いので(0.6〜0.8kmほどのところが多い)、歩いて歩けなくもありません(電車が通ればなお便利)。
「目蒲線」の方は目黒駅〜丸子駅(現・沼部駅)間が敷設された年(大正12年)の11月には終点の蒲田駅まで通じています(目黒駅と蒲田駅が繋がって「目蒲線」と呼ばれる)。当時はおそらく単線で、車両数も少なく(1両?)、スピードもさほど出なかったでしょうから線路も今ほど堅牢に作る必要もなく、短期間で敷設できたのでしょう。
 |
蒲田駅近くに「松竹蒲田撮影所」ができたのは大正9年ですが、3年後(大正12年)に蒲田駅から目黒駅まで電車が通じ(「目蒲線」)、8年後(昭和3年)には蒲田駅から五反田駅まで電車が通じ(「池上線」)、その沿線がロケ地としてふんだんに利用されるようになったことでしょう。
昭和7年に公開された小津安二郎監督の蒲田映画(松竹蒲田撮影所で製作された映画)「生れてはみたけれど」(Amazon→)は、冒頭から、「目蒲線」「池上線」沿線を思わせる開発中の住宅地が出てきます。また、「池上線」の電車が所々で顔を出します(この頁の一番上の写真も参照)。とても面白い映画ですが(「キネマ旬報ベスト・テン」第1位)、それとは別に、映画は時代の記録としても貴重ですね。
 |
 |
| 「生まれてはみたけれど」の一場面。「池上線」の電車が通る。戦後の旧3000系と同じように、窓枠あたりが明るい色に見える | 「生まれてはみたけれど」の一場面。電車は一両編成でまるでオモチャのよう。カメラを回した |
昭和9年公開の島津保次郎監督の蒲田映画「隣の八重ちゃん」はホームドラマの元祖的な作品です。「目蒲線」の田園調布駅あたりのモダンな住宅街が舞台になっています。
昭和37年公開の小津安二郎の最後の映画「
 |
 |
| 「秋刀魚の味」の一場面。「池上線」の石川台駅で電車を迎える二人。案内板の「ゆきがやおおつか」「ISHI(KAWADAI)」「せんぞくいけ」の文字が確認できる(photo→) | 「秋刀魚の味」の一場面。踏切を通過する「池上線」の電車。濃いグリーンがメインで、窓枠あたりがオレンジ。昭和26年から昭和41年まで走っていた旧3000系だろう。近年(平成28年)復刻され、時々このデザインの電車が走るようだ |
昭和51年、西島三重子さん(25歳)の2枚目のシングル「池上線」(作詞:佐藤順英、作曲:西島三重子、編曲:馬飼野俊一。ワーナー・パイオニア Amazon→)が大ヒットし、今も歌い継がれています。歌が生まれるような沿線っていいですねぇ。
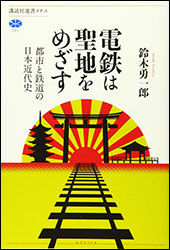 |
 |
| 鈴木勇一郎 『電鉄は聖地をめざす 〜都市と鉄道の日本近代史〜(講談社選書メチエ)』。成田山新勝寺、川崎大師、穴守稲荷神社、池上本門寺といった寺社仏閣興隆の願いと電鉄敷設との深〜い関係 | 鹿島 茂『小林 |
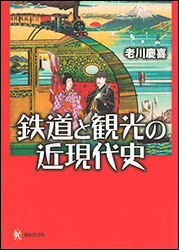 |
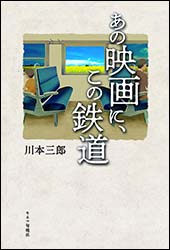 |
| 川本三郎『あの映画に、この鉄道』(キネマ旬報社) |
■ 馬込文学マラソン:
・ 小池真理子の『欲望』を読む→
■ 参考文献:
●『大田区史年表』(東京都大田区 監修:新倉善之 昭和54年発行) P.440、P.443、P.446 ●『小津安二郎物語』(厚田雄春、蓮實重彦 筑摩書房 平成元年発行)P.181-182 ●「大正期の大森・蒲田・羽田/近代工業の展開」(山本貞男)※『大田区史(下)』(東京都大田区 平成8年発行)P.273 ●『電鉄は聖地をめざす(講談社選書メチエ)』(鈴木勇一郎 令和元年初版発行 同年発行2刷参照)P.132-134、P. 154-157 ●『嬉遊曲、鳴りやまず 〜斎藤秀雄の生涯〜(新潮文庫)』(中丸美繪 平成14年発行)P.105-122
※当ページの最終修正年月日
2022.6.26