| {column0} |

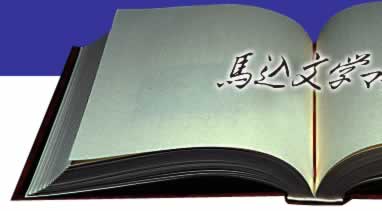







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
「隣の八重ちゃん」の一場面。八重ちゃんが友だちを連れて家に帰ると、隣の恵太郎が一人でご飯を食べている・・・ ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用
 |
島津保次郎 |
昭和9年6月28日(1934年。
蒲田にはもう一人有名な「やすじろう」(小津安二郎)がいましたが、こちらの「やすじろう」も蒲田を代表する監督。この「隣の八重ちゃん」は島津の代表作の一つに数えられています。
松竹初期の大監督は小山内 薫と野村芳亭、島津は小山内の門下生として入所した第2世代です。
「隣の八重ちゃん」は、当地の田園調布(東京都大田区田園調布 Map→)の2家族の交流を描いたもので、ホームドラマの元祖的作品です。田園調布といえば今や高級住宅街の代名詞ですが、映画ができた昭和9年頃は分譲が始まってから日が浅く(大正12年8月(関東大震災の1ヶ月前)から分譲が始まった)、“田園”の趣を残していました。そこの服部家には2人の娘(その次女が八重ちゃん)がいて、隣の新井家には2人の息子(その長男が帝大生でハンサムな恵太郎)がいます。両家族は父親や母親も含めて親しくしています。恵太郎が「なんかお腹減ったなぁ」みたいなことを言うと、隣の服部家のおばさん(八重ちゃんのお母さん。演:飯田蝶子)がお茶漬けなどを出してくれます。その代わりに恵太郎は服部家のお留守番。そこに娘の八重ちゃんが友だちを連れて帰ってきます(上の写真を参照)。そのくらい仲のいい両家族なのでした。
八重ちゃん(演:
オープンでフレンドリーな両家庭のあり方に、観客はさぞ憧れたことでしょう。
映画が日本に入ってきたのは明治末で、明治32年には日本人が撮影した映画も作製・公開されました(浅野四郎の短編映画「化け地蔵」「死人の蘇生」)。その後、観客数増加に応じて、作製される作品数も増え、映画は、テレビが普及する昭和35年頃まで、日本人の最大の娯楽となりました(映画の最盛期の昭和33年の国民1人あたりの年間鑑賞数は12.3回、平均すると1ヶ月に1回映画館に足を運んだ計算になります)。映画は、人々の感情に敏感に反応しつつも、新しい生活スタイルも提案。人々は大いに感化されたことでしょう。
紹介した2作品(「隣の八重ちゃん」「生まれてはみたけれど」)のように、ホームドラマには、新しい生活の提案があり、従来からの家庭を舞台にした作品(可憐な母親の悲劇を描く「母もの」など)とは一線を画しました。
 |
木下惠介 |
「隣の八重ちゃん」の撮影助手に木下惠介が名を連ねています。戦中(昭和18年)に映画監督デビューした木下は、戦後、テレビドラマにも参画、昭和43年から翌年にかけて放送された「木下惠介アワー」の第4弾「3人家族」(脚本は山田太一。山田は松竹で木下に師事した。島津→木下→山田という師弟関係)などは昭和30年代生まれの日本人の家族観に多大な影響を及ぼしたことでしょう。男だけの3人家族と女だけの3人家族があって、最初、それぞれの家族の次男と次女が気安い関係になります。その気安い関係が、それぞれの家族の長男(演:竹脇無我)と長女(演:栗原小巻)の大恋愛を成就を助け、さらには、それぞれの家族の父と母をも結びついていくという、ちょっとあり得ませんが、すごくいい話です(笑)。テレビは映画以上に身近で、より広く影響を及ぼしたことでしょう。
理想の家庭の提案でもあったホームドラマに、大きな変化があるのはいつ頃でしょう。理想はやはり理想であって、もっと現実を見つめようとの方向性が顕著になるようです。
 |
昭和52年に放送された原作・脚本:山田太一のテレビドラマ「岸辺のアルバム」は衝撃的でした。多摩川近くに住む一見平穏な家庭が崩壊するまでが描かれます。専業主婦で家に閉じこもりがちで夫や子に置いてけぼりにされていると感じ始める妻と、会社のエゲツない生き残り作戦についていけず悩む夫と(妻に相談できない)、憧れていた米国の米国人に凌辱される姉と(家族に相談できない)、そんなてんでんバラバラの家族をなんとかしたいのに受験勉強に引き裂かれていく弟。最後には、多摩川があふれ、家まで流されてしまいます(放送3年前(昭和49年)の多摩川の水害がモデルになっている)。しかし、その時から、「家族の再生」も始まるのでした・・・。
 |
 |
| 「隣の八重ちゃん」(松竹)。ジャケット写真の右上が |
坂本佳鶴惠『<家族>イメージの誕生 〜日本映画にみる<ホームドラマ>の形成〜』(新曜社)。家族のイメージがどう形成・変遷してきたか映画でたどる |
 |
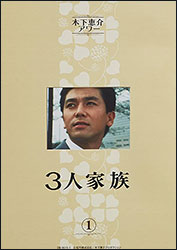 |
| 長部日出雄『天才監督 木下惠介(新編)』(論創社)。黒澤 明と人気を二分した木下の実像に迫る。全49作品のスチール写真と詳細な年譜も収録 | 「3人家族」(松竹)。企画:木下惠介・山田太一。脚本:山田太一。出演:竹脇無我、栗原小巻、あおい輝彦、沢田雅美、三島雅夫、賀原夏子ほか |
■ 参考文献:
●『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.102-104、P.226-238 ●「『隣りの八重ちゃん』『婚約三羽烏』(レビュー)」(嶋田丈裕)(TFJ's Sidewalk Cafe→) ●『<家族>イメージの誕生 〜日本映画にみる<ホームドラマ>の形成』(坂本佳鶴惠 新曜社 平成9年初版発行 同年発行2刷参照)P.83、P.105
※当ページの最終修正年月日
2024.6.28