| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
橋本平八の天女(左)と佐藤玄々の天女(右)
 |
昭和35年4月19日(1960年。
日本橋三越本店(東京都中央区日本橋
佐藤が三越と契約したのは9年まえの昭和26年(佐藤62歳)。京都の妙心寺大心院(京都府京都市右京区花園妙心寺町57 Map→)の庭に仮設のアトリエを建て制作に入りました。3年後(昭和29年)に原寸大の模型ができますが、その時点では6メートほどの高さでしたが、さらに3年すると10mを突破、アトリエも大改造が必要になりました。中央の天女から制作に入り、上下左右に装飾部が広がっていったようです。最初に全体の大きさを定めないのは、松本キミ子さんが編み出した作画法「キミ子方式」を思わせます。
佐藤の故郷は福島県相馬市中野(Map→)です。海への思いが深かったのでしょう。福島の支援者にカスべ(エイ)、ホッキ貝を送ってもらい、上下左右の装飾部の造形の参考にしたそうです。「まごころ像」の前に立ってば、「福島の海」が聞こえるでしょうか。
昭和20年5月24日から翌25日にかけて、当地(東京都大田区馬込)を襲った空襲で、佐藤はアトリエと住居を全焼、多くの作品を失いました。心血を注いだ作品を一挙に失う絶望はいかばかりか。それだけに、「まごころ像」へかけた思いは尋常でなかったと想像されます。除幕式の3年後の昭和38年、佐藤は、「まごころ像」に全生命力を捧げたかのように、その制作場所の大心院で息を引き取りました。75歳。
完成が7年も遅れたことに佐藤とそのスタッフ(延べ10万人が制作に携わった)の苦労がしのばれますが、三越もよく待ったものです。佐藤の才能を信じ、それを支えました、「天下の三越」の威信をかけて。
「芸術は万人のもの」との考えに立つと、「まごころ像」は理想的です。 入場料なぞ払わないで、そこに行けば、いつでも偉大な芸術に会うことができるのですから。下から見上げるもよし、2階、3階、4階から眺めるもよし、5階から見下ろすもよし。それぞれ違った表情を見せてくれることでしょう。
 |
 |
| 「まごころ像」の全体。この「過剰」はただごとでない | 後光(装飾部)に目がくらむが、天女はちゃんと降臨している |
もう一つ、佐藤の大作を、皇居のお堀端で、無料で鑑賞できます。「
 |
橋本平八 |
佐藤の重要な功績の一つは、彫刻家・橋本平八(明治30年〜昭和10年)を育てたこと。橋本は、大正9年から大正13年までの5年間、当地(東京都大田区馬込)の佐藤のアトリエに住み込み、佐藤から彫刻を学びました。佐藤も橋本から影響を受けたようです。
橋本は北園克衛の実兄です。橋本は大正13年に当地を去って郷里の三重に戻りましたが、代わりに、北園が、昭和9年から、佐藤のアトリエのすぐ近くに住み始めています。佐藤と北園も何らかの交流があったのでしょうか?
 |
橋本平八の「花園に遊ぶ天女」。佐藤のとはずいぶん違うが、これも「天女」(photo:陳寅恪) ※クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際ライセンスのもと利用が許諾されている 出典:ウィキペディア/橋本平八(令和4年4月9日更新版)→ |
橋本が住み込んだ期間の大正11年10月より1年9ヶ月間ほど、佐藤(34-35歳)は、美術院の奨学金で、パリのブールデルの美術研究所に通い、ジャコメッティーとも交遊しています。
ところで、人類はいつ頃から像を作っているのでしょう。
発見されている中で一番古い彫刻は、3万年ほど前(旧石器時代。日本では無土器時代とも)、狩猟民が洞窟の壁に刻んだレリーフ状(浮き彫り状)の彫刻で、フランスの「アングル・シュル・ラングラン」(Map→ 参考site→)のものなどが知られています。野生の動物と一緒に、やはり(佐藤や橋本の「天女像」同様)女性が彫り込まれています。多産や豊穣を願う気持ちが形になったものなのでしょう。少しすると立体的な彫刻も現れますが、やはり女性を象ったものが多く見られるようです(「ヴィレンドルフのヴィーナス」など)。西岡秀雄は、こういったセクシャルな像(男根を象ったものなども多い)を性神ととらえ学究しました。西岡は当地の「大田区立郷土博物館」(東京都大田区区南馬込五丁目11-13 Map→)の初代館長ですが、同博物館は、実は、「まごころ像」の作者・佐藤のアトリエ跡に建っています。
日本では、縄文時代の土偶が最古の彫刻のようです。古墳時代になると副葬される埴輪が盛んに造られ、仏教が伝来すると(
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖典『旧約聖書』の
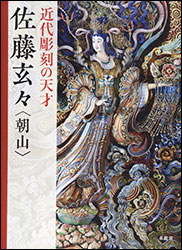 |
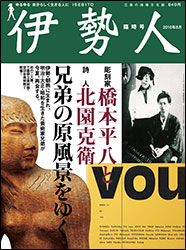 |
| 『近代彫刻の天才 佐藤玄々<朝山>』(求龍堂)。編集:増渕鏡子、坂本篤史、北川智昭、小川貴史 | 「伊勢人(159号)」(伊勢文化舎)。特集「彫刻家・橋本平八 詩人・北園克衛 〜兄弟の原風景をゆく」 |
 |
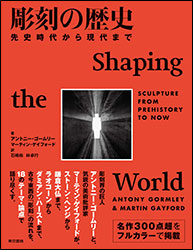 |
| 矢内原伊作『ジャコメッティ手帖 1』(みすず書房)。編集:武田昭彦ほか。著者・矢内原がジャコメッティに初めて会ったのは昭和30年11月8日。矢内原はパリから帰国するのを伸ばし、以後、計230日間、モデルを務めた。矢内原(矢内原忠雄の息子)も幼少期を当地で過ごしている | アントニー・ゴームリー、マーティン・ゲイフォード『彫刻の歴史 〜先史時代から現代まで〜』(東京書籍)。訳:石崎 尚、林 卓行。世界的な彫刻家と、注目の批評家が対話形式で、古今東西の彫刻を語り尽くす。世界各地の遺跡に刻まれた彫刻からジャコメッティ、ブランクーシといった現代作家まで |
■ 馬込文学マラソン:
・『北園克衛詩集』を読む→
■ 参考文献:
●「橋本平八の入門」(増渕鏡子)、「佐藤玄々年譜」(増渕鏡子) ※『近代彫刻の天才 佐藤玄々<朝山>』(求龍堂 平成30年発行)P.23、P.49、P.140-144、P.168-178 ●『佐藤朝山と近代彫刻論』(磯崎康彦 玲風書房 平成24年発行)P.3、P.126-127 ●「彫刻の歴史/西洋」(三田村
※当ページの最終修正年月日
2025.4.19