| {column0} |

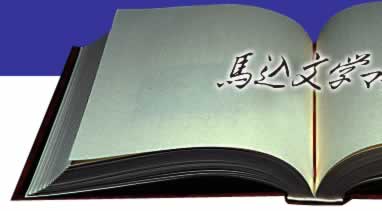







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和29年6月9日(1954年。 萩原葉子(34歳)が、子どもの頃、家族を置いて出奔した母親の居場所が分かり、札幌へ会いに行っています。
昭和4年、葉子が9歳の頃、父・萩原朔太郎と自分たち二人の子ども(
会うと、母親は、予想以上に老いており、それなのにまだ 「女」 をふんぷんとさせており、葉子をそれを嫌悪しました。20も若い資産家と暮らしていて、若かった頃の自分を盛んに自慢。葉子のことを行儀が悪いとなじり、こき下ろし、「冗談とは思えない冷たさ」がありました。
ことに、父親の朔太郎の悪口を言われるのが葉子には辛かった。そのときのことを、葉子は『
・・・「見てごらん! やっぱり似ているじゃないの」
急に
左の頬にいきなり、なま暖かいものがふれ、私は母に頬をすり寄せられていた。 強い母のにおいが、不快だった。
「見てごらんってば!」 我慢している私に母はじれったそうに、肩をゆすぶる。
“萩原に似て
「血」─なんという厭なことばだろうか。その一言で、母から抜け出せないもので縛られてしまったようだ。・・・(萩原葉子 『女客』 より)
それまでも、葉子は、「血」に苦しめられてきました。
母親・稲子が出奔した後、葉子は、祖母のケイ(朔太郎の母親)から「おまえにも母親と同じ淫乱な血が流れている」といった嫌がらせを言われ続けてきたのです。
「血」を理由に
母親に会いに行った昭和29年頃、葉子は離婚交渉の真っ最中でした。昭和19年に職場の上司と結婚しましたが、二人は考えが合わず、いつも激しくいさかい、夫はいつも不機嫌で、暴力に出ることもありました。若い頃から話し相手がいなかった葉子は本を読むことが唯一の救いでしたが、小説は主婦を堕落させると言って夫はそれを取り上げたそうです。母親の居場所が分かるのは、夫との関係もいよいよという頃でしょうか。考えてみたら(当たり前ですが)、家族と言っても夫(伴侶)とは血が
「血が繋がっている」ことからの結束力は小さくなく、子どもなどは特にその血縁の中で無条件に受け入れられ、そこに
葉子はもっとも母親を必要とする子どもの時に、その母親に置き去りにされたのですから、心に負った傷はいかばかりだったでしょう。
しかし、「母性」がいいことづくめかというと、全くそんなことはなく、戦後になってからでしょうか、子どもの家庭内暴力などの問題行動から(夫の家庭内暴力は戦前から多かった?)、子どもの自立を
葉子の場合は、母親(「母性」)にこがれながらも、上記のような母親だったため、「母性」の負の面にも気づき、それに反発しやすかったかもしれません。案外“いい母親”が曲者で、子育てに一途な自分に問題があるとは思いいたらず、子どもも自分の自立を阻んでいる「母性」の負の面に気がつかず、それとの対決をズルズルと遅らせがちになるかもしれません。そして、子どもの意識・無意識に負の感情が蓄積されて、ときには爆発し、ときには鬱屈して病んでいったり。
 |
萩原葉子が母親と対決したように、志賀直哉は父親と対決しています。
志賀は1,700坪あまりの邸宅(東京都港区六本木四丁目3-13 map→ ※案内板あり)に家族と住んでいましたが、大正元年11月10日(志賀29歳)、家を出て、広島の三軒長屋(尾道市東土堂町8-28 map→ ※見学可能)で一人暮らしを始めます。
志賀は18歳頃から父親と対立していました。志賀が足尾銅山の鉱毒問題に関わることに、祖父が同山の経営に参画していることを理由に父親が猛反対したのです。血が繋がっている(親族だから)という理由で批判を許さない父親を志賀は軽蔑しました。祖父は志賀と父親との争いを静観し、父親の肩をもつこともなかったそうで、そんな祖父を志賀は敬愛します。父親との確執とその後の和解が、志賀の大きな文学的テーマとなりました。志賀は明治40年(24歳)頃、結婚の問題でも父親と衝突しています。戦前は概して「家」が絶対で、父親(戸主)の考えに反発するのは“不良”でしたが、いちはやく個人に目覚めた人たちはそれと対決します。
個人や家族や同族が自らの生命や生活をギリギリの線で保持していくために、「血」という呪術めいた観念で結束する必要があった時代もあったでしょう。でも今や、そんな野蛮な時代ではないはずですから、「理解」による結束に重きが置かれて良いはず。日本はまだまだ「血」に縛られる側面が強いような気がします。
「生みの親より育ての親」という言葉があります。“赤毛のアン”、マシューおじさん、その妹・マリラに、「血」がどれだけの意味があったでしょう?
「母性」や「父性」の発現者は、親である必要もないでしょう。山本周五郎は勤め先の主人を「真実の父」と呼び、「血」のつながる父よりもずっと敬愛しました。
 |
 |
| 河合隼雄『家族関係を考える (講談社現代新書)』 | 斎藤 学『家族依存症 (新潮文庫)』 |
 |
 |
| 小林敏明『父と子の思想 〜日本の近代を読み解く〜 (ちくま新書) 』 | 寺山修司『家出のすすめ (角川文庫)』。人生に行き詰まったらこれ? |
■ 馬込文学マラソン:
・ 萩原葉子の『天上の花』を読む→
・ 萩原朔太郎の『月に吠える』を読む→
・ 志賀直哉の『暗夜行路』を読む→
・ 山本周五郎の『樅ノ木は残った』を読む→
■ 参考文献:
●『
■ 謝辞:
●俳優のH.K様より励ましのお言葉をいただきました。ありがとうございます。
※当ページの最終修正年月日
2023.6.7