| {column0} |

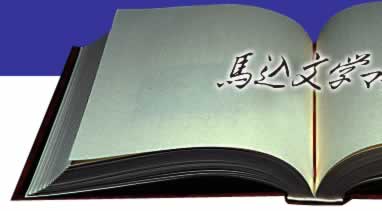







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和9年5月18日(1934年
北條民雄(19歳)が、東京東村山村の
自立志向が強く、高等小学校卒業後、郷里の徳島から東京に出て、薬問屋や工場で働き自活しましたが、16歳頃、兆候が現れ、昭和8年(18歳)、郷里でハンセン病と診断されます。すでに結婚していましたが破婚。再び上京し、五反田をへて、当地(東京市蒲田区町屋町。現・東京都大田区西六郷一丁目 Map→)に住んでいる時、全生病院への入院を決意しました。
全生病院に入院した一日目のことを題材にして書かれたのが『いのちの初夜』です。
・・・今こうして黙々と病院へ向って歩くのが、自分にとって一番適切な方法なのだろうか、それ以外に生きる道は無いのであろうか。そういう考えが後から後から突き上って来て、彼はちょっと足を停めて林の梢を眺めた。やっぱり今死んだ方がよいのかも知れない。梢には傾き始めた太陽の光線が、若葉の上に流れていた。明るい午後であった。・・・(北條民雄『いのちの初夜』より)
主人公の尾田は一人病院に向かいながら、木の枝ぶりが気になってしようがありません。首をくくれそうな枝を探すのがその頃の彼の習い性になっていました。そのくらい、ハンセン病になることからくる絶望は深いものがあったのです。感染者は顔や手足が崩れるといった後遺症を残すことがあることから、怖がられ、不当に差別され、不当に排斥されていました。
実際には、北條は、昭和9年5月18日、父親に付き添われて全生病院に向かっています。死への誘惑はありませんでしたが、病院へ向かう駅の駅頭で、「不意に頭上に堕ちてきた棒」をくらいます。荷物が多かったのでタクシーを使おうとしますが、乗車を拒否されたのです。病気に対する不安もさることながら、こういった差別がいかにこたえることか。
そして、10万坪もあったという病院の敷地を囲む逃亡防止のための
 |
| 今も残る柊の垣根 |
北條はこの柊の垣根の内側で、昭和12年12月5日に結核で死去するまでの3年と6ヶ月あまりの間、生きる意味を必死に探り、多くの文章を残しました。北條の文学を最後まで見守り育てた川端康成の存在も大きいです(川端は北條の訃報を聞いて病院に駆けつけた。その後『北條民雄全集』の編纂に携わる)。
北條の作品は、川端はじめ、横光利一、島木健作、青野
以後のハンセン病患者の文学者たちは、この北條と、北條より13歳年上でやはり高く評価された歌人・
敗戦後1年した昭和21年、日本国憲法が制定されて「基本的人権」が保証されることとなり(とはいっても、非人間的な強制収容の条項を持つ「らい予防法」が廃止されるのはずっと後で、平成8年になって)、また、翌昭和22年には、ハンセン病の初の治療薬プロミンが輸入されるようになって(ハンセン病は治る病気となった)、患者たちに大きな希望が生まれます。
戦前から療養所内に公認の文学サークルがあり園の機関誌などを発表の場にしていましたが、戦後になると、独自のサークル誌が生まれます。全生園でも、園公認の全生詩話会に対抗し、若き書き手たちが『
・・・せめて
指よ
芽ばえよ。
一本、二本多くてもよい。
少くてもよい。
乳房をまさぐった
かえれ
この手に。・・・
(森 春樹「指」より)
と、絶望には違いないのに、ユーモアや、官能も詠み込まれ、
・・・ときどき空をみる。
鬼瓦よ。
地上に僕という小さな
おまえの顔もすごいな。
おまえの顔の後に月がいる。
おまえの上を鳥が飛ぶ。
鬼瓦よ。
おまえをみていると僕は勇気がでる。
呪詛する勇気。
その中に微かな純血性がある。
太陽と
気流の層。
鳥は飛ばなければならぬ。
獣は地を這わねばならぬ。
僕は、歩かねばならぬ。・・・
(
と、おおらかに大胆に言葉が選択され、確固とした意思が表現されます。
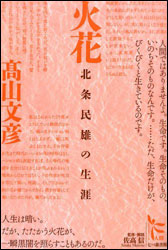 |
 |
| 高山文彦『火花 〜北條民雄の生涯〜』(七つ森書館)。監修・解説:佐高 信。年譜あり | 『明石海人歌集 (岩波文庫)』。編集:村井 紀。もっと生きたら昭和を代表する歌人になったろうと大岡 信に言わしめた海人。その絶望から放たれた「光」 |
 |
 |
| 『詩集 いのちの芽(復刊)』(国立ハンセン病資料館)。編:大江満雄、木村哲也。全国のハンセン病療養所にいた73人の作品。「世界の癩に関する年譜」付き | 伊波敏男『ハンセン病を生きて 〜きみたちに伝えたいこと〜 (岩波ジュニア新書) 』。「差別や偏見は、真実を知らないことから生まれる」 |
■ 馬込文学マラソン:
・ 川端康成の『雪国』を読む→
■ 参考文献:
●「北條民雄年譜」(光岡良二 昭和55年作成)※『定本 北條民雄全集(下)』(東京創元社 平成8年発行)に収録 ●『柊の垣のうちから』(北條民雄)※『定本 北條民雄全集(下)』(東京創元社 平成8年発行)に収録 ●『詩集 いのちの芽』(編:大江満雄 国立ハンセン病資料館 令和5年初版発行 同年発行2刷参照)P.238、P.262、P.266-267、P.271、P.277 ※「解説」(大江満雄)、「世界の癩に関する年譜」、「解説 『いのちの芽』復刊に寄せて」(木村哲也)
■ 参考映像:
●「100de名著/名著127「いのちの初夜」北條民雄」(NHK 令和5年2月6日初回放送)(コメンテイター:中江有里、司会:伊集院 光、安部みちこ)紹介サイト→
※当ページの最終修正年月日
2023.5.18