| {column0} |

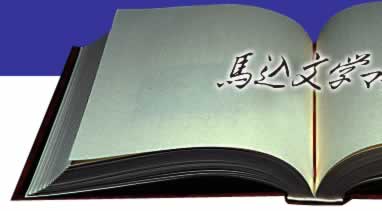







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
映画ファンは「マダムと女房」で田中絹代の声を初めて聞いた ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 出典:映画「マダムと女房」(松竹)
昭和6年8月1日(1931年。 、日本初の本格的トーキー「マダムと女房」(松竹)が「帝国劇場」(東京都千代田区丸の内三丁目1-1 Map→)で封切られました。
トーキー(talkie)は、talking pictureからできた言葉で、音の出る映画の意味。それまでの無声映画(サイレント)に対し「発声映画」ともいわれます。
米国のリー・デ・フォレストがトーキー技術(「フィルム方式」。映像のフィルムに音の情報も焼き付ける)の特許を取ったのが、12年前の大正8年。6年後の大正14年、
その後、昭和キネマの配給を担当していた東条政生が、昭和3年、昭和キネマを離脱して「ディスク方式」のトーキー技術を開発します。レコードに録音し、フィルムと同時に再生する方式です。
両者は試行錯誤し試作品を作りましたが、トーキーの効果を十分には生かせず、興行的にも成功しませんでした。
米国では、ワーナーが大正15年、サウンド版(映像と音楽の映画。会話は入らない)の「ドン・ファン」を公開、翌昭和2年には世界初のトーキー(部分的なトーキー)「ジャズ・シンガー」を成功させ、翌昭和3年にはオールトーキーの「シンギング・フール」を公開。世界的には、昭和の初めから本格的なトーキーの時代に入っていました。
 |
松竹蒲田撮影所の所長の
しかし、言葉とは裏腹に、城戸は、「日本初のトーキーは蒲田で」との決意を固めており、帰国直後から動きました。やる気がないようなことを言ったのは、他社の対抗心を刺激しないためでしょう。松竹トップ(松竹を創業した白井松次郎と大谷竹次郎。両者の松と竹をとって松竹)の了承を得て、大阪道頓堀の松竹座で楽士をしていた
そして、蒲田で、本格的トーキー制作が始まり、2年後の昭和6年、日本初の本格的トーキー「マダムと女房」の上映とあいなりました。
監督は
現在のようなアフレコ(後時録音)や複合録音(複数の録音を合成)の技術がないので、セリフ、伴奏、効果音を同時に録音しなくてはなりません。雑音が入らないよう細心の注意が必要でした。ステージの天井と壁に布をはり、床には畳を敷いて反響を防ぎました。下駄の音、近くの工場の音、チンドン屋、豆腐屋の笛、カメラの回転音などにも気を配りました。豆腐屋に笛を遠慮してもらうために撮影所で豆腐を買いとり、大量の豆腐をスタッフは家への土産にしたというエピソードが残っています。カメラの回転音を消すためにカメラマンは公衆電話のボックスのようなブースに入って撮影したそうです。
 |
渡辺 篤 |
初トーキーということで、音が印象的な効果を出すようなストーリーになっています。締め切り間近の原稿を抱えた劇作家(演:
極め付けは隣家からのジャズの音。たまりかねて劇作家は隣家に抗議に行きます。ところが、歓迎され、彼はすっかりジャズバンドとジャズシンガー(隣のマダム。演:伊達里子)の虜になってしまうのでした。そして、家に戻ると、ジャズの軽快なリズムに乗って仕事がトントン拍子に進み、めでたく原稿が仕上がる、といった他愛のないコメディーです。最後の方で、希望・未来の象徴として飛行機の音が響きます。「女房とマダム」の公開日のおよそ1ヶ月後(昭和6年8月25日)、「東京飛行場」(現・羽田空港)が開港します。テスト飛行している飛行機の音でも拾ったのでしょう。初めから終わりまで音にこだわっています。
 |
女房役の田中絹代(21歳)の声は、下関
 |
 |
| いつまでも寝ている劇作家の顔の上で鳴り響く目覚まし時計を振り回す娘(演:市村美津子) ※「パブリックドメインの映画(根拠→)」を使用 |
トーキーにいち早く挑戦した皆川芳造の発声映画株式会社は、「マダムと女房」公開の翌月(昭和6年9月)に解散しました。一種の敗北宣言でしょう。
小津安二郎も蒲田の監督でしたが、トーキーを撮り始めるのは、5年も後(昭和11年)です。トーキーを撮るにあたり、小津にはあるこだわりがあったのです。
 |
 |
| 「「マダムと女房」、「春琴抄」(監督:島津保次郎、田中が出演) 」 | 田中純一郎『無声からトーキーへ(日本映画発達史 II)(中公文庫』 |
 |
 |
| 「ジャズ・シンガー」(ワーナー・ブラザーズ)。スクリーン上で俳優が初めてセリフを喋った記念すべき作品。和田 誠の映画の名セリフ集『お楽しみはこれからだ』(Amazon→)の書名は、「ジャズ・シンガー」の中のセリフ | 「雨に唄えば」(MGM)。サイレントからトーキーへの転換期をパワフルに生きる3人。ジーン・ケリー、デビー・レイノルズ、ドナルド・オコナーほか。作中に「ジャズ・シンガー」も。「ミュージカル映画ベスト」(アメリカ映画協会)の第1位 |
■ 参考文献:
●『小説 田中絹代』(新藤兼人 読売新聞社 昭和58年初版発行 昭和61年発行23刷)P.112-122 ●『人物・松竹映画史 蒲田の時代』(升本喜年 平凡社 昭和62年発行)P.162-182 ●『わたしの渡世日記(上)(文春文庫)』(高峰秀子 平成10年初版発行 平成23年発行12刷)P.42
※当ページの最終修正年月日
2023.8.1