| {column0} |

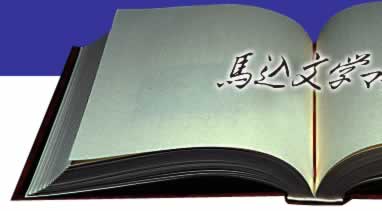







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
明治10年9月24日(1877年。 、モース(39歳)が、東京大学で進化論を講じ始めたようです。日本で進化論が本格的に講じられるのはおそらく初めてでしょう。
話が分かりやすく、ユーモアもあり好評で、その後も、学外でも個人に請われたりして、モースは進化論を講じています。
講義したときのことをモースは次のように記しています。
・・・聴衆は極めて興味を持ったらしく思われ、そして、米国でよくあったような、宗教的な偏見に衝突することなしに、ダーウィンの理論を説明するのは、誠に愉快だった・・・
キリスト教国では、「旧約聖書」に基づいて(イスラム教でも「旧約聖書」は啓典(預言者に下された啓示の書)なのでイスラム教国でも?)、万物は神が創造したと考えられてきたので、長い時間を経て生物の形質が変化するという「進化」という考え方(「進化論」)に対して、聖職者を中心に激しい反発がありました。日本にも、イザナギとイザナミが日本列島を創成したとする「国生み」の神話がありますが、神が万物を創造した話はないようで、また、日本人は、土俗的な神(例えば「山の神」といったもの)や仏教の仏なども渾然と受け入れ、宗教感情に柔軟性があって、「進化論」もすんなり受け入れたのかもしれません。
同年(明治10年)に来日したモースは、大森貝塚の発見で有名ですが、来日の目的は、日本に豊富に生息する
モースが腕足動物に興味をもった理由は、この生き物は6億年前(古生代初期。先カンブリア紀)から現在にいたるまでほとんど形質に変化がなく“生きている化石”と呼ばれ、「進化論の反証」ともされていたからです。「反証」を調べ、進化論をバージョンアップしようとしたのでしょうね。
 |
 |
| 腕足動物のミドリシャミセンガイ ※「東京大学総合研究博物館」の展示物。当館はモースが大森貝塚で発掘した土器や人骨なども所蔵、見学できる。入館料は無料。ボランティアガイドによる説明もあり、おすすめ ●東京大学総合研究博物館→ | モースが描いたシャミセンガイ。腕足動物は触手冠という構造を持つ ※「パブリックドメインの図版(根拠→)」を使用 出典:『私たちのモース』 原典:ピーボディー博物館特別展「Japan Day by Day」図録 |
------------------------------------------------------
 |
 |
アガシー |
ダーウィン |
日本に来る18年前(1859年)モース(21歳)は、米国の動物学の第一人者アガシー(52歳。スイス生まれ。氷河期の発見者)に請われてその助手になりますが、奇しくもその年、ダーウィン(英国。50歳)が『種の起源』を出版、進化論を世に問うたのでした(勝 海舟らが咸臨丸で米国に渡航する1年前ですから、そんな昔の話でありません)。進化論は「突然変異と自然淘汰のプロセスを繰り返して進化する」 というもので、神が万物を創造したとするキリスト教的生物観と真っ向から対立するものでした。アガシーは動物学者でしたが牧師の息子ということもあって、進化論に反対でした。モースも最初はアガシー同様進化論を否定しましたが、2年後の1861年(モース23歳)には、アガシーの元を去ります。明治3年頃(モース32歳頃)腕足類を軟体動物とは別類の触手動物と分類し、明治6年(モース35歳)には進化論支持を明言、翌明治7年からは積極的に進化論を講じるようになります。来日した明治10年(モース38歳)には、すっかり進化論論者でした。
ダーウィンもケンブリッジ大学で神学を学び牧師を目指したくらいですから最初、進化論など夢想だにしなかったでしょうが、1831年(ダーウィン22歳)から5年間にわたり英国海軍の測量船ビーグル号に艦長の話相手として乗船、南米沿岸を移動中、ガラパゴス諸島などの島々で動植物の様相がわずかずつ変化することに気づいて、生物が環境に適応して変化すると考えるようになります。環境に適応した形質を持つ個体がより多く生き延びて、その形質がより多く子孫に遺伝、その種が進化すると考えました。自然がその適応した個体を選んだとして「自然選択」と呼ばれます。
1669年、ニコラウス・ステノが提唱し現在広く受け入れられている「地層は下にあるものほど古くに形成された」という考えに則ると、最初、地球には、植物や魚類などのみが出現し、徐々に爬虫類、鳥類、ほ乳類などが出現してきたとなります(下の方の古い地層にはほ乳類などの化石がない)。魚類などから人間などのほ乳類が進化したという考えも生まれました。
進化論には「遺伝」という考え方が前提として必要です。ダーウィンよりも65年も前に生まれたラマルクは、環境に応じて必要な形質を獲得し、必要ない形質は衰退するという進化論の先駆けともいえる「用不用説」を唱えましたが、それらの形質が遺伝することを検証できず評価されませんでした。
子が親に似ることは分かっても、ラマルクの時代(1744-1829年)はもちろんのことダーウィンの時代(1809-1882年(明治15年))にも、遺伝のメカニズムは分かっていませんでした。その糸口を掴んだのがメンデル(独。1822-1884年(明治17年))です。多くの生物は細胞の中に遺伝子を含む染色体をペアで持っており、その染色体の片方が配偶子(卵子や精子)に入って、その配偶子が合体することで再び染色体をペアでもつ個体になることと、ある比率を持って両者の形質が遺伝される仕組みを解明しました。
「ダーウィンの進化論」(ダーウィニズム)だけでは説明できないこともたくさんあります。例えば、生物の多様性。自然淘汰によって進化が進むのなら、環境に適応した限られた生物だけになりそうですが、地球には昆虫だけでも175万種以上もいるそうです。限られた状況では自然淘汰もあるのでしょうが、トータルに自然を理解するには、共存や協働の概念も必要になってきます。また、ダーウィンと同時代を生きたファーブルが指摘したように、生物の神業ともいえる精妙な行動を知ると、それらが進化によって獲得されたものとは到底考えられません。元から備わっている「本能」に着目する必要がありそうです。
なお、ダーウィニズムを社会現象に当てはめた「社会進化論」(ソーシャル・ダーウィニズム)が、その「自然淘汰」「生存競争」「適者生存」などの理論で、帝国主義や優生思想やナチズムなどの暴力的民族主義を正当化してきました。今でも、それに近い言説を垂れ流す政治家もどきや学者もどきがいるので注意が必要です。他国を指して「後進国」などと呼ぶのも「社会進化論」に十分に毒されています。第一、大量兵器で他国を威圧したり、工業製品や商品を乱生産して地球を破壊しまくったりする国が「先進国」であるわけありませんよね?
 |
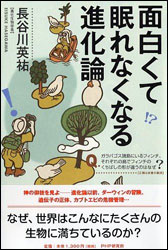 |
| ダーウィン『種の起源〈上〉 (光文社古典新訳文庫)』。訳:渡辺政隆 | 長谷川英祐『面白くて眠れなくなる進化論』(PHP研究所)。平成27年発行 |
 |
 |
| 今西錦司『進化とはなにか (講談社学術文庫)』。種の棲み分けによって種単位に進化したと説く今西進化論。ダーウィニズムの「問題点」をえぐる | 吉川浩満『理不尽な進化 〜遺伝子と運のあいだ〜』(朝日新聞社)。絶滅という視点、通俗的な進化論の特徴と問題点などをユーモアを交えながら |
■ 参考文献:
●『私たちのモース ~日本を愛した大森貝塚の父~』(編・発行:東京都大田区立郷土博物館 平成2年発行)P.12-22、P.26-29、P.38-44 ●『面白くて眠れなくなる進化論』(長谷川英祐 PHP研究所 平成27年発行)P.3-29、P.30-48、P.52-55
■ 参考サイト:
●左側のない男/ファーブルはなぜ進化論に否定的だったか→
※当ページの最終修正年月日
2021.9.22