| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
「布晒舞図(ぬのさらしまいず)」。英 一蝶が流刑先の三宅島(Map→)で、遊興三昧の日々に思いを馳せ描いもの(全体図→) ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:『英 一蝶(日本の美術 1 No.260)』 原典:「遠山美術館」(Site→)所蔵作品 ※原画を素材にして構成した
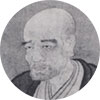 |
宝永6年8月21日(1709年。
庭に目をやると蝶が一匹庭先の草花で戯れており、その時、赦免の報せが届いたのが不思議で、画名「一蝶」という名を思いついたと伝わっています。この赦免を機に、これまで使っていた画名「
一蝶が、なぜ、島流しされたのでしょう?
一蝶は、太鼓持ち(宴席で座を盛り上げる職業)としても有名で、遊び仲間の
宝永6年1月(1709年)、綱吉が天然痘で死去するや、6代将軍・徳川
 |
「吉原風俗図巻」(部分)。三宅島に流されて5年して描いたもの。半玉が客に呼びかけ、話がついて相手をする女性を呼んだところか? ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:『英 一蝶(日本の美術1)』(至文堂) |
一蝶が生まれたのは、
上でも触れた通り、一蝶が生まれた1650年代を境に時代は大きく変っていきます。武力を背景に全大名を幕府に従わせる体制を整えた3代将軍・徳川家光が1651年に死去したあと(一蝶の誕生はその翌年(1652年))、4代将軍・徳川家綱以降は、武断から文治へと政策が大きく転換。封建的な武家からの圧力が弱まって、上方を中心に町人文化が伸長し、古典的な雅な文化も復興してきます。町人の文化は「俗」のテイストも大切にしました。そんな時代の流れの中で、近松門左衛門、井原西鶴、菱川師宣らが出てきます。一蝶が20代の頃、浮世絵の創始者・菱川師宣が頭角を現し、驚くべき絶倫男・浮世之助が登場する井原西鶴の『好色一代男』(浮世草子の第1作)が刊行されたのが、天和2年(1682年)、一蝶が30歳の時です。遊里や芝居町などいわゆる「悪所」を絵画や文芸の題材にすることを世間一般は受け入れ、師宣も西鶴も時代の寵児としてもてはやされたことでしょう。そして、爛熟した元禄期(1688-1704)の文化へと突入していきます。
明暦3年(1657年)の江戸の大半を灰にした大火事「明暦の大火」(焼死者が10万人を超えた)が、明日のこと(命)は分からないので、今をバッと楽しんでしまえといった一種享楽的な感情に拍車をかけたかもしれません。「江戸っ子は宵越しの金を持たない」と言われますが、「明暦の大火」後も度々ある江戸の大火事をへた人々の口の端に上った言葉が元になったのではないでしょうか。
「俗」や享楽の追求は、精神の解放をもたらすとともに、精神の頽廃にも繋がりかねません。特に統治者は、人々の「俗」や享楽への傾斜を警戒しそれを抑圧することが多いでしょう。5代将軍・綱吉の儒教を元にした施政はまさにそうだったのでしょう。その煽りを食って、風俗画家であり太鼓持ちの一蝶も島流しになった。
一蝶が三宅島に流されている
江戸に戻った一蝶は、東京深川の霊岸寺門前に住み、仏師民部や村田半兵衛ら悪友とまたつるんで(両者は一蝶より罪が重いとされ、三宅島より遠方の八丈島(Map→)に流されたが、やはり赦免となった)、大商人(樽屋三右衛門、奈良屋茂左衛門、紀伊国屋文左衛門など)のところに出入りし、彼らの遊興を助けています(笑)。
 |
| 「雨宿図屏風」(部分)。様々な身分・職業・年代が集う場面を一蝶は好んで描いた。よく見ると犬もいる(Photo→)。退屈した子どもは柱にぶら下がったり(Photo→)、破れ傘から覗いたりして遊んでいる(Photo→) ※「パブリックドメインの絵画(根拠→)」を使用 出典:文化遺産オンライン(文化庁)/雨宿り図屏風(英一蝶)→ |
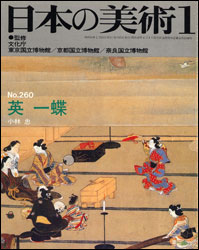 |
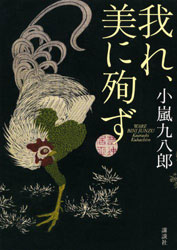 |
| 小林 忠『英 一蝶(日本の美術 no.260)』(至文堂) | 小嵐九八郎『我れ、美に殉ず』(講談社)。地位を捨てて美に殉じた江戸時代の4人の絵師。英 一蝶についても |
 |
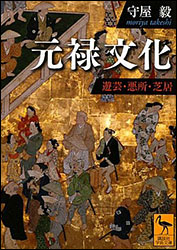 |
| 『風俗画の展開 (辻 惟雄集 第4巻) 』(岩波書店) | 守屋 毅『元禄文化 〜遊芸・悪所・芝居〜 (講談社学術文庫)』 |
■ 参考文献:
●『本朝画人伝(下)』(村松梢風 中央美術社 大正15年発行)P.54-55(NDL→) ● 『英 一蝶(日本の美術1 No.260)』(小林 忠 昭和63年発行)P.17-29 ●「胡蝶の夢」(田所義行)※「日本大百科全書(ニッポニカ)」(小学館)に収録(コトバンク→) ●『詳説 日本史研究』(編集:佐藤
※当ページの最終修正年月日
2023.8.21