| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和24年9月11日(1949年。
6人の男が岩宿(群馬県みどり市
2ヶ月前の7月縄文層より下位の地層(縄文時代より古い時代の地層。関東ローム層)から明らかな形を有した石器を発見した相沢忠洋(23歳)と、考古学研究のために相沢の元に通ってきていた高校生2人(加藤
発掘(試掘)は9月11日から13日までの3日間行われますが、その1日目の夕方の5時前、杉原が縄文層より下位の地層から楕円形の「
関東ローム層(ロームとは粘性の高い土壌)は、地質時代の「第四紀」(「人類の時代」)の「更新世」(かつては聖書のノアの箱舟にちなんで洪積世と呼ばれた)の中期以降、富士山、箱根山、浅間山、赤城山、男体山といった火山からの降下物(火山灰など)で形成されたもので、1万年でおよそ1m堆積、厚い所だと10mを越すとのことです。この地層が形成された時代は火山活動が活発で人が住める状態でなかったと考えられていましたが、石器が見つかったことでその認識が覆されました。この縄文時代以前の時代を「無土器時代」「
過去にも、
 |
相沢忠洋 |
発見時の様子を相沢が次のように書いています。
・・・午後もだいぶ時間がすぎ、掘りかえした土の山が崖のふちにたまってきたころには、
突然、杉原先生が、
「出たぞ、出たぞっ」
と大声で叫んだ。先生は小型スコップを捨て、削られた崖面に素手をひろげている。みんないっせいに先生のところへ走り寄った。先生が指さす褐色層の断面に、みずみずしい青色の石のはだが覗いている。それも比較的大きいようである。みんなは息をのんだ。先生は指で少しずつまわりの粘土状の土をていねいに払いのける。だんだんその青色の石は大きくあらわれ、卵型の形を見せてきた。やがてコロッと先生の手で掘り出された。先生が指で泥を払いのけると、なんと、完全なりっぱな石器であった。
みんな、かたずをのむ。先生は無言でしばらくなでまわしていた。その手はふるえているようだった。・・・・(中略)・・・私は、この新しい学問の出発点をみつけ出すことに貢献できた喜びを、心のなかで一人かみしめるのだった。・・・(相沢忠洋『「岩宿」の発見』(講談社)より)
 |
| 岩宿で発掘する6人。左から3人目が相沢。すると、左の2人が高校生の加藤と堀越か 出典:『「岩宿」の発見 』(相沢忠洋 講談社) |
この時見つかった握斧はおよそ紀元前3万年前のものと推定されています。紀元前1万5千年くらいから縄文時代が始まるので(縄文時代草創期の青森県「
近年では、紀元前12万年ほどの遺跡(島根県「
紀元前12万年前というと大昔のようですが、「猿人」(人類の祖先)は紀元前500万年よりも前に出現しており、「旧石器時代」は人類の歴史からするとずっとこっち寄りということになります。「猿人」はすでに直立二足歩行で手が自由に使えていたと考えられるので、石器の類を利用していたと推測でき、遺跡・遺物が発見されれば「旧石器時代」の始まりは限りなく紀元前500万年に近づいてゆくことでしょう。
6人での共同発掘の2ヶ月前(昭和24年7月)、相沢が掘り出した石器(槍先形石器。日本で初めて発見された「旧石器時代」の石器)は、黒曜石でできていました。黒曜石は産出される場所が限られており、岩宿のある群馬県では産出されません。黒曜石の産地、長野県の和田峠(
モースが当地(東京都大田区)で「大森貝塚」を発見し縄文時代という歴史区分が考えられるようになるのが明治10年(1877年)で、その7年後(明治17年。1884年)、帝大の学生だった坪井正五郎らが弥生式土器を発見し弥生時代が考えられるようになりました。相沢が縄文層の下部より石器を発見して日本にも「旧石器時代」があったことが分かるのは、ぽんと飛んで昭和24年(1949年)、弥生土器の発見から65年も経ってのことでした。
相沢らに続いて日本各地で「旧石器時代」の遺物が発掘されるようになり、当地(東京都大田区)でも、「
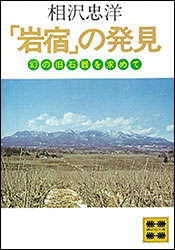 |
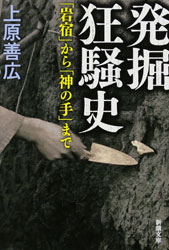 |
| 相沢忠洋『「岩宿」の発見 〜幻の旧石器を求めて〜 (講談社文庫) 』。幼少時は鎌倉の寺に一人預けられ、履物屋に奉公にも出され、その後、行商をしながら発掘、「岩宿」の発見に至る | 上原善広『発掘狂騒史 ~「岩宿」から「神の手」まで~(新潮文庫)』。当初、無視・誹謗された相沢の発見を最初に高く評価したのが芹沢長介。芹沢と「旧石器捏造事件」との関係とは? |
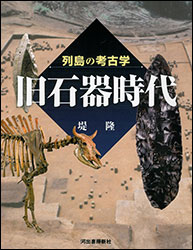 |
 |
| 堤 隆『旧石器時代 〜列島の考古学〜』(河出書房新社) | 篠田謙一『人類の起源 〜古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」〜(中公新書)』 |
■ 参考文献:
●『発掘狂騒史 〜「岩宿」から「神の手」まで〜(新潮文庫)』(上原善広 平成29年発行)P.26-28、P.54-76 ●『「岩宿」の発見』(相沢忠洋 講談社 昭和44年発行)P.20-32、P.56-59、P.194-208 ●『そのとき何歳?(伝記 人物ものがたり)』(編:講談社 平成24年発行)P.46-47 ●「デジタル大辞泉/大平山元遺跡」(小学館)(コトバンク→) ●『詳説 世界史研究』(編集:木下康彦、木村靖二、吉田 寅 山川出版社 平成20年初版発行 平成27年発行10刷参照)P.7 ●『詳説 日本史研究』(編集:佐藤
※当ページの最終修正年月日
2024.10.30