| {column0} |









(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
昭和45年6月16日(1970年。 三島由紀夫(45歳)にあてた石原慎太郎(37歳)の書簡「政治と美について」が、「毎日新聞」で公開されました。5日前の6月11日、同紙夕刊に掲載された三島の石原あて公開書簡「士道について」に対する反論です。
 |
石原は、2年前の昭和43年(35歳)、参議院議員選挙に自民党の公認で全国区で出馬、史上最高の301万票を集めて初当選を果たしていました。
この書簡の形式をとった2人の公開討論の発端は、2週間前の6月2日、「諸君!」(文藝春秋社の月刊オピニオン誌)に掲載された、石原と京大助教授の
社会、民社、共産、公明そして無所属ならざる人間の集団ですよ。(笑)
と応え、次のようにも言います。
政治というものの本体は、
本当に事なかれです。それで何をやっているかというと、結局は役人に協力しているだけなんだな。
と。
 |
そんな石原に三島は「士道について」を書きました。石原・高坂対談があった9日後(6月11日)です。次のような文面です。
永年の良友である貴兄に公開状など出すのは愉快なことではないが事柄が公的な性質のものなので・・・(中略)・・・私はこの(「諸君!」の)対談を二度読み返してみて、貴兄がさういふ半党的(!)言辞を
欺瞞と考える集団に自らも属しながらその欺瞞を指摘するのは、つまりはその欺瞞そのものではないかと。そして、書簡のタイトルにある「士道」を例に、三島流の行動美学を開陳します。
・・・昔の武士は、藩に不平があれば
そこに属してなにがしかの有利を得ている者がその集団についてブツクサいうのは醜いので止めなさい、言うのならそこを離れてからにしなさいということでしょう。
この“説教”に対して、5日後の6月16日に、石原が反論したわけですが、これがなかなか冴えてます。
率直にいって、三島氏の公開状を読んで
三島さんも、その
文中の「メタモルフォルゼ(メタモルフォーゼ)」はドイツ語で「変形・変質」のことで、「ファルス」は喜劇のことで、「マヌカン」がマネキン(人形)のことでしょう。
たしかに、武士が諌死(死んで
個人を集団の上位概念にしているのが新鮮です。集団に属する個人がその集団のおかしいところを指摘するからこそ、集団が健全に分裂もし、併合もし、発展もし、衰弱もするということでしょう。
前年(昭和44年)11月にも、三島と石原が「守るべきものの価値」というテーマで対談していますが、三島の「あなたは何を守つてる?」との問いに対して石原は、ズバリ、
ぼくは、やはり自分で守るべきものは、あるひは社会が守らなければならないのは、自由だと思ひますね。
と応えています。石原は個人の自由を尊ぶ人だったのですね(他者の自由を尊ぶかは別として・・・)。
集団といっても、生得的にまたは自然と所属するもの(例えば家族、学校のクラス、地域集団など)と、自ら選択して所属するもの(サークル、政党、交際グループなど)とでは、全く性格が異なりますが、概して「日本人は集団主義」と言われ続けています。
日本国内では、その「集団主義」がプラスイメージで語られることも多いようです。日本人は「集団主義」が身についているから、我がままや文句などは言わずに集団のために尽くし(和を第一にして)、成果を上げてきたのだと。明治時代に短期間に近代化を達成したのも、戦後、高度経済成長を遂げたのも、個人よりも集団を優先するパーソナリティを日本人が有していたからと理解している人もいるかもしれません。または、集団の大勢の行動パターンを規範としてそれに合わせて行動し、それから外れることを極度に
ところが、個人主義や自由主義が民主主義の根幹と考える欧米(特に米国)では、「集団主義」はほぼ100%マイナスイメージのようです。欧米では集団主義とは集団のために個人が犠牲になることであり、「没個性」とは魅力のない人間の代名詞でもあるようです。言葉を変えると、一人では何もできないとなり、言われたことはロボット的にこなせても発展的思考は苦手(苦手というより人と違うことを憚るのでそれを避ける)となります。日本国内でも、「いじめ」はその集団主義が異質なものを排除しようとする働きであると説明されるようになってきました。
 |
 |
| H.C.トリアンディス『個人主義と集団主義 〜2つのレンズを通して読み解く文化〜』(北大路書房)。翻訳:神山貴弥、藤原武弘 | 高野陽太郎『「集団主義」という錯覚 〜日本人論の思い違いとその由来〜』 (新曜社)。各種日本人論(大体が「日本人は集団主義」)を検証 |
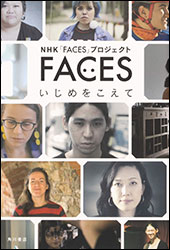 |
 |
| 『FACES 〜いじめをこえて〜』(KADOKAWA)。著:NHK「FACES」プロジェクト | 太田 肇『同調圧力の正体 (PHP新書)』。物事を批判すると、すぐ「仲良くやろぜ」の声がわく |
■ 馬込文学マラソン:
・ 三島由紀夫の『豊饒の海』を読む→
■ 参考文献:
●『五衰の人』(徳岡孝夫 文藝春秋社 平成8年初版発行 平成8年2刷参照)P.10-32 ●『「集団主義」という錯覚 〜日本人論の思い違いとその由来〜』(高野陽太郎 新曜社 平成20年初版発行 同年発行2刷参照)はじめに、P.1-22
※当ページの最終修正年月日
2022.6.16