| {column0} |

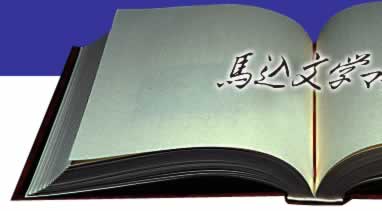







(C) Designroom RUNE
総計-
本日-
昨日-
| {column0} |
 |
昭和22年2月7日(1947年。 原 民喜(41歳)が当地(東京都大田区)より、広島の姉(原 すみ江)に手紙を書いています。
お手紙有難うございました。
寒はあけたのに、まだまだ寒いことですが、皆さんは御元気の様子何よりと存じます。先日帰郷の際は何彼と御世話になり有難く御礼申上げます。とても大変な汽車でしたが
増岡登三郎氏のことについては、美樹君に先便で申上ましたが、まああんな人なのですから仕方がないでせう。荷物は先方から発送してくれることと思います。それにしても早く美樹君の宿が見つかるといいのですが。
先日も永井君が逗子の方へ探してやるとは
新新円が出るといふ噂も御座いますが、何が飛び出してくるやら全く日本の前途は暗澹としてゐます。
寒さの折、御大切に。皆さんによろしく御伝へ下さい。
姉上様 二月七日 民喜
原は、昭和19年9月28日、最大の理解者だった妻の貞恵を病で喪い、千葉の家を引き払って、故郷広島に帰って家業を手伝っていましたが、昭和20年8月6日、そこで被曝します。便所にいたため大きな怪我もなく、生き延び、翌昭和21年、中学時代からの友人・長 光太の誘いがあって上京。長の家((現在「馬込幼稚園」(東京都大田区南馬込二丁目25-11 Map→)があるあたり)に寄寓中、上の手紙を書きました。
被曝したのは生家(兄・信嗣の家)で、爆心から1.2kmしか離れていないのに、目から出血があったものの大きな怪我がなかったのは、奇跡的と言えるのかもしれません。原は直後から手帳に原爆直後の惨状を記し、そのメモを元に、その年(昭和20年)の秋から冬にかけて『夏の花』を執筆しました。
広島の次兄の家に居候しますが厄介者扱いされ、本も読みずらく、そこに、長からの上京を勧める手紙が届いたのです。翌昭和21年には「三田文学」が復刊し、「近代文学」も創刊され、それらに書くことと、何よりも『夏の花』をそれらに掲載する
玄関近くの階段を上がった3畳ほどの部屋でした。木のベットがあるだけで、原は、石油缶を机がわりに執筆します。慶應義塾商業学校・工業学校の夜間部の嘱託英語講師と、「三田文学」の編集に携わりますが、収入は極めて少なく、蔵書や大切な服まで売って飢えをしのぎましたが体重は36kgまで落ちました(身長は164cm)。
私のいま使っている机は、──机ではなく実は箱なのだが、下に石油箱を横たえ、その上に木製の洋服箱を重ね、書きものをする高さに調節している訳なのだが、この上の方の軽い箱には
私は昨年の二月、千葉の家を引上げ、郷里の兄の許に移ると、土蔵の中で、この箱を見つけた。妻が嫁ぐとき持って来た品々は、まだその土蔵の長持の中に
貞恵と出会ってからの原は、何を見ても貞恵との思い出に連なり、また、全ての物語は貞恵のことから生み出されていったのかもしれません。上に引用した『
昭和21年9月28日、妻・貞恵の2度目の命日となりました。久しぶりに床屋へ行って、大森駅前の池上通りに出た頃、貞恵の臨終の時刻となり、原は、決断して、梨と林檎を買い求めました(大森駅西口前の果物屋「西村」はもうあっただろうか?)。果物を買うのに「決断」が必要なほど、原は貧しかったのです。
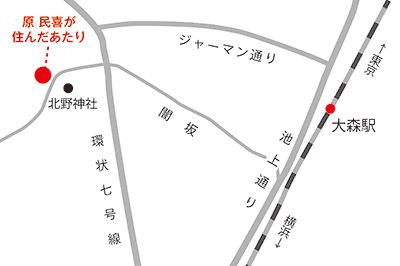 |
原が住んだのは、「北野神社」(東京都大田区南馬込二丁目26-14 map→)の真向かいあたり。当時はジャーマン通りが明瞭でなかっただろうから、大森駅前の池上通りに出るのに
|
梨と林檎を3畳の部屋に持ち帰って、石油缶に置いて長い間眺めていた原。
長と妻は不仲で、長は札幌への出張に出たまま帰ってこなくなります(長は記録映画制作の仕事をしていた。札幌で好きな女性ができる。原とはその後も頻繁に文通)。原は長の妻から洗面所や井戸を使うことを禁じられ、洗面器に水を入れてゴミ捨て場に行って顔を洗ったといいます。それでも長の家に留まったのは、それこそ行くところがなかったからなのでしょう。
昭和22年5月頃に長の妻から追い出された原は(1年ほどは当地にいたことになる)、長兄方の甥・茂の下宿(東京都中野区)に一時的に転がり込みます。『夏の花』を「三田文学」に発表したのはその6月。
『夏の花』は、妻の最初の命日を前にして、妻の墓を訪れる場面から始まります。
私は街に出て花を買ふと、妻の墓を訪れようと思つた。ポケットには仏壇からとり出した線香が一束あつた。八月十五日は妻にとつて初盆にあたるのだが、それまでこのふるさとの街が無事かどうかは疑はしかつた。
“夏の花”は、一人の人間(原の場合は妻の貞恵)のかけがえのない生と死とを象徴し、その後の原爆は、それとは対照的な、「死者16万人超」とか人数で語られる人間(その一人一人にもかけがえのない生と死があったはずだが)を象徴します。このグロテスクなまでのコントラストが『夏の花』の骨格なのでしょう。
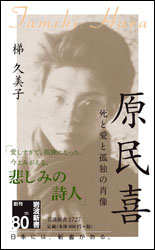 |
 |
| 梯 久美子(かけはし・くみこ) 『原 民喜 〜死と愛と孤独の肖像〜 (岩波新書) 』 | 原 民喜 『夏の花・心願の国 (新潮文庫)』 |
 |
 |
| 川西政明『文士の戦争、日本とアジア (新・日本文壇史 第6巻) 』(岩波書店) | 『三田文学名作選 〜創刊100年〜』(三田文学会) |
■ 参考文献:
●『定本原 民喜全集Ⅲ』(青土社 昭和53年発行)P.233-243 ●『原 民喜〜死と愛と孤独の肖像〜(岩波新書)』(梯 久美子 平成30年発行)P.154-160、P.197-206、「原 民喜略年譜」 ●『原 民喜(人と文学)』(岩崎文人 勉誠出版 平成15年発行)P.119-120
※当ページの最終修正年月日
2025.2.7